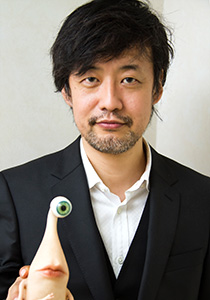3・11後の日本だからこそ伝わる映画『寄生獣』の世界観—ヒットメーカー・山崎貴監督
文化- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ハリウッドが映画化権を握っていた「伝説」のコミック
人間の体が未知の生命体に侵略されるといえば、米国SF作家ジャック・フィニイの名作『盗まれた街』を基にハリウッドが何度も映画化した『ボディ・スナッチャーズ(The Invasion of Body Snatchers)』を思い起こす映画ファンもいるだろう。家族や友人がいつのまにか人間ではなくなっているという不気味さは、映像化への意欲をそそる素材なのかもしれない。そのハリウッドが原作権を獲得したものの、ついに映画化に至らなかったのが、人間の脳を乗っ取るパラサイトと人間たちの戦いを描いたコミック「寄生獣」だ。
岩明均原作の人気コミックは1989年から1995年にかけて連載され、単行本は累計発行部数1500万部を突破。ハリウッドが長らく原作権を保持していたが、映画化が実現しないまま権利が日本に戻った。このコミックを、VFX(特殊視覚効果)第一人者で数々のヒット作を放ってきた山崎貴監督が2部作の実写映画版『寄生獣』として完成させた。前編は2014年11月に公開され、観客動員150万人突破のヒット、4月25日には完結編が公開される。
ジェームズ・キャメロン監督『T2』に影響?
「連載当時、すでにVFXの仕事を始めていましたが、この作品は絶対誰かが映画化する、その際は仲間に入れてもらおうと、自分の顔の映像を撮って、顔がグシャッと崩れてまた元に戻る様子をデジタル化したデモフィルムまで作りました。でも、結局誰もやると言い出さなかった」と山崎監督は振り返る。
当初、映画業界人の間でウワサになっていたのは、原作コミックを知っていたジェームズ・キャメロン監督が、『ターミネーター2』を撮るがために「寄生獣」の権利を買い取ったという説だ。「一種の“都市伝説”ですよ。でも、確かにT-1000(『T2』に登場する液体金属製のボディを持つターミネーター)が、寄生獣にインスパイアされたような動きをする。影響は受けていると思います」。
実際に映画を撮る過程で、ハリウッドがなぜ実写化に踏み切らなかったのかを改めて考えてみたという。「多分善悪がはっきり分かれていないからじゃないかな。キリスト教的な考え方だと、納得できない話なんです。多神教の日本では、寄生生物たちが人間より上位の(一種の)“神”だと捉えることもできる。誰が悪で誰が善なのか判然としない、あるいは、個人の中にすべて内包しているという描き方は、アメリカではわかりにくいのかもしれない」。
 主人公の泉新一を演じる染谷将太(左から2人目)は、2011年ベネチア国際映画祭のマルチェロ・マストロヤンニ賞(最優秀新人賞)を受賞した実力派だ。(C) 2015 映画「寄生獣」製作委員会
主人公の泉新一を演じる染谷将太(左から2人目)は、2011年ベネチア国際映画祭のマルチェロ・マストロヤンニ賞(最優秀新人賞)を受賞した実力派だ。(C) 2015 映画「寄生獣」製作委員会
「寄生獣」の主人公・泉新一はごく普通の高校生だ。ある日未知の生物に右手を食われ、そこに寄生したパラサイトとの共生を余儀なくされるが、やがて奇妙な友情がそのパラサイト“ミギー”との間に芽生える。新一・ミギーと人間を捕食して人間に擬態するパラサイトたちとの、種の存亡をかけた壮絶な戦いが繰り広げられる。
この主人公の在り方がまさに日本的だと、山崎監督は言う。「主人公が二つの種族の中間にいるというのは、極めて日本的です。仮面ライダーしかり、ウルトラマンしかり、デビルマンしかり…。一見ハリウッドのインベーダーもの、“乗っ取りもの”の流れをくむようにみえるが、『寄生獣』の世界観は日本独特だなと、作っている過程で実感しました」。
ゲーム業界の最新技術で実現した寄生生物のリアルさ
20年以上前、最初に「寄生獣」の映画化に参加したいと思った頃と比べれば、VFX技術は飛躍的に進化した。しかし、日本の映画界は「保守的な世界で、なかなか最新技術が下りてこない。つまり、そこに予算をかけていいかジャッジできる人がいない。僕ならわかる。(ミギー役の)阿部(サダヲ)さんの持っている資質を100%ミギーに生かすためには、パフォーマンスキャプチャーを使うべきだと思った」。
今回、寄生獣の“顔割れ”シーン(脳を食われた人間の顔が真っ二つに割れてパラサイトが現れる)やパフォーマンスキャプチャー(動きだけではなく顔の表情まで一括してCGにとりこめる技術)を活用するにあたり、ゲームメーカーのコナミ、スクウェア・エニックスの協力を得た。
 パフォーマンスキャプチャースーツを着て、新一の右手に寄生するミギー(右)を演じる阿部サダヲ。(C) 2015 映画「寄生獣」製作委員会
パフォーマンスキャプチャースーツを着て、新一の右手に寄生するミギー(右)を演じる阿部サダヲ。(C) 2015 映画「寄生獣」製作委員会
「最先端の優れた技術がゲームメーカーにある。しかし、ゲーム業界までアンテナをはっている監督はほとんどいない。今回も、そもそも映画に関係ない人たちのところに押しかけて、日本映画のために貸してくれと頼みこんだわけです。使わせてもらうのは大変だったが、いい結果が出ました」
ハリウッドではトライアル・アンド・エラーを重ね、ベストの方法を選択する。繰り返し使うことで、技術も向上していく。だが、「日本では予算の制限もあり、あの技術ならきっと役に立つと見当つけて進めるしかない。勇気もいるし、(最新技術を持つ)業界にアンテナをはっていないとできない」。
「3・11」後の日本だからこそ伝わるメッセージ
だが、「寄生獣」を日本で映画化する機が熟していたと感じたのは、技術面だけではない。「作品が警鐘を鳴らしていることが、現実的に起きている。作品を今映像化することで、何かのメッセージを伝えられる気がするんです」。
 日本映画界を担うそうそうたる役者たちが『寄生獣』に出演している。前編では若手人気俳優の東出昌大(左)がパラサイト高校生を演じた。(C) 2014 映画「寄生獣」製作委員会
日本映画界を担うそうそうたる役者たちが『寄生獣』に出演している。前編では若手人気俳優の東出昌大(左)がパラサイト高校生を演じた。(C) 2014 映画「寄生獣」製作委員会
 寄生生物と特殊部隊の対決場面を演出中の山崎監督。(C) 2015 映画「寄生獣」製作委員会
寄生生物と特殊部隊の対決場面を演出中の山崎監督。(C) 2015 映画「寄生獣」製作委員会
原作コミックの連載当時は、作品の地球環境問題への警鐘が注目されていた。しかし今は、自分たち人間の存続に対する危機感があり、「よりせっぱつまった状況の中で、この原作が内包していたメッセージはすごいなと改めて思っている」と言う。
「いつまた大地震がくるか、放射能は、本当はどうなっているのかなどと、非常に不安定な日常の中で、おびえながら生きている。そうした状況の中でこそ語られるべき物語なのではないか。それを政治的メッセージではなく、今、日本に住んでいる人間として、エンターテインメントの中で伝えることに意義を感じた」
『寄生獣』は4月末に開催されるイタリアのウディネ・ファーイースト映画祭で上映される。「海外の観客は、この映画に3・11後の日本が色濃く影を落としていることを感じ取るだろうし、人間がいかに罪を背負いながら、それでも生きていくという思いは、共感を得られるのではないかな」。
海外を意識しすぎると足元をすくわれる
 八木竜一監督と共同監督した3DCGアニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』は世界興行収入100億円を突破。
八木竜一監督と共同監督した3DCGアニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』は世界興行収入100億円を突破。
「昭和の東京」を再現して大ヒットした『三丁目の夕日』シリーズを始めとして、「宇宙もの」「時代劇」「戦争もの」「3DCGアニメ」と、毎回違う世界をVFXで描き、ヒット作を重ねてきた。エンターテインメントとしての日本映画界の第一人者だが、国際マーケットにおけるコンテンツとしての日本映画には、冷静な判断をしている。
「コンテンツをインターナショナルに育てようという気はそれほどない。海外を意識しすぎると足元をすくわれる。僕らはアジア人で、英語がベースの文化でもないし、ハンデが多い。アジア人が主役を演じている以上、実写映画でハリウッドのブロックバスターと張り合おうとするのは無理。ただし、戦えるジャンルはあると思う。時間は限られているのだから、できるだけ勝てるカードで戦いたい。例えば3Dアニメなら、多くの国で受け入れられるベースはある」
「そもそも国際マーケット自体が最終目標ではなく、ガラパゴスと呼ばれる日本市場でどういう勝負をしていくかが、今の自分としては大事。それがたまたま国際的競争力もっているものなら、どんどん出していきたい。それはあくまでも副次的、“ボーナス”です」
VFX畑の出身であり、多様なジャンルの作品でさまざまな技術を使ってきたが、映画を撮る際に重視するのは、最新技術への挑戦ではない。
「色々なオファーをもらいますが、一貫しているのは、オファーを受けた瞬間に、これは自分で撮りたいと血がたぎる思いがしたものばかりです。技術はその時に必要なものが使えればいい。大概なことはCGでできてしまうので、今更、誰も驚いてくれない。まずは物語があって、そこで描かれるキャラクターが魅力的であることが一番大事です」
(2015 年4月13日都内でインタビュー)
聞き手・文=板倉 君枝(編集部)