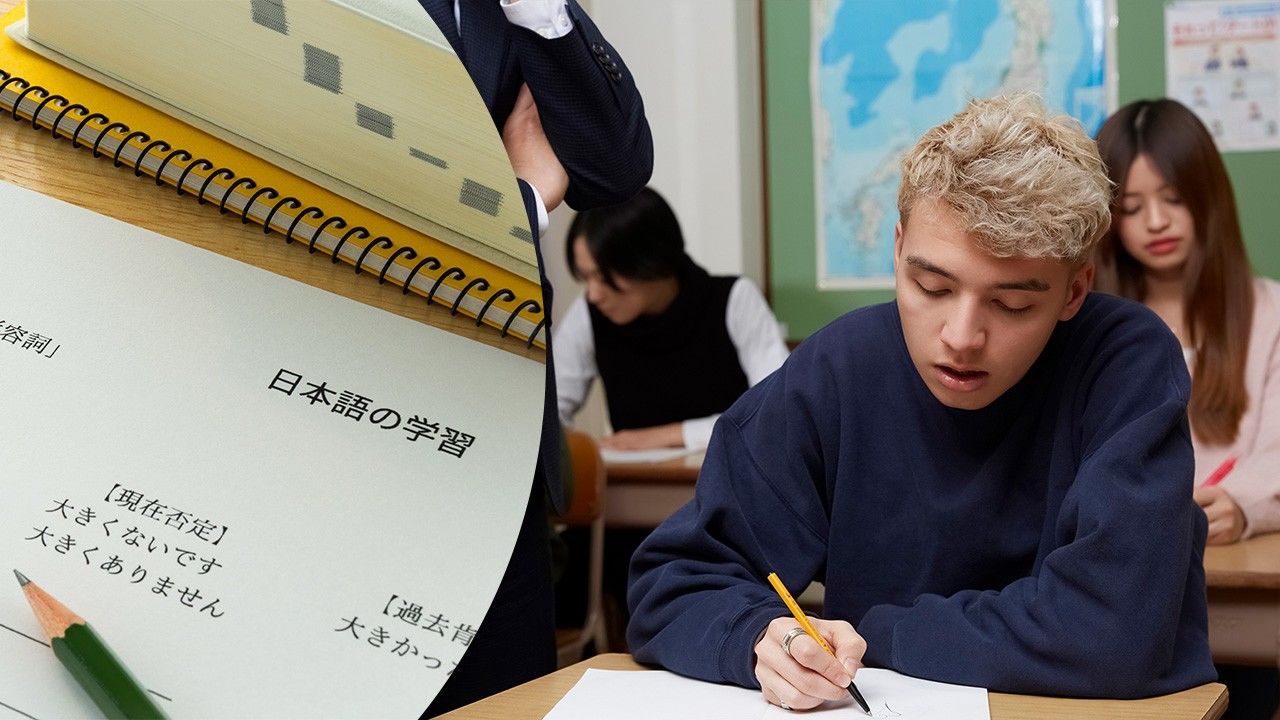
待ったなしの日本語教育改革:高まるニーズの中で課題山積、険しい「質向上」への道
社会 教育 仕事・労働- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本語学校の新たな認定制度
2024年末、日本の外国人留学生は40万人に到達した(出入国在留管理庁)。23年3月に岸田文雄内閣は10年後までに留学生を40万人受け入れる目標を掲げたが、2年を経ずして達成された。その中には、日本の大学、専門学校への進学や日本企業への就職を目指す日本語学校在籍者も含まれる。その数は、9万人超(23年5月1日現在)で過去最高、法務省が認可した日本語学校(=告示校)は全国に約870校ある。10年前の2倍超だ。
一方で、日本語学校を隠れみのに、アルバイト目的で来日する“偽装留学生”が多いとかねてから指摘されてきた。実際、不十分な在籍管理や不適切な入学選考を繰り返してきた学校は少なくない。また、「日本語の指導をするために必要な知識及び技能を十分に有しない者が指導」したり、「不十分な施設・設備に多数の外国人を受け入れ」たりする状況がある(文部科学省「日本語教育機関の認定制度の創設」)。
こうした問題意識を背景に、2024年4月、「日本語教育機関認定法」が施行された。日本語教育の所管が文化庁から文科省に変わるとともに、法務省が行ってきた認定審査を同省が担う。「就職コース」「進学コース」など学生の目的に合わせた教育課程の編成、教職員の体制、施設・設備、学校運営の経済的基盤、留学生募集時に第三者に払う仲介料の金額の妥当性、設置者の日本語教育に対する見識や経営知識、社会的信望といった細かい要件をチェックする。
これまでの「告示校」は、29年3月末までに認定を受けなければ、留学生を受け入れられなくなる。25年3月末時点で、認定申請した日本語学校120校(新設を含む)のうち、41校が認定された。
また、日本語教員が認定校に勤務する場合、新たな国家資格「登録日本語教員」の取得が義務付けられた。これまでは民間資格で、「日本語教師養成講座」修了(4年制大卒以上)、「日本語教育能力検定試験」合格、または大学で日本語教育履修のいずれかの要件を満たせば勤務できた。24年11月に初めて実施された登録日本語教員の試験では、約1万8000人が受験、1万1000人が合格した。
政府が推し進めた受け入れ拡大
日本で最初に実施された留学生政策は、1983年、中曽根康弘首相が打ち出した「留学生受け入れ10万人計画」だ。当時の在日留学生は1万人程度だった。親日派・知日派を増やし、開発途上国の人材育成にも貢献することで、国際社会で日本のプレゼンスを増す意図が背景にあった。
政府はビザ発給手続きを簡素化し、私費留学生を積極的に呼び込む方策として、資格外活動にあたるアルバイトの規制を緩和し、日本語教育の推進も掲げた。結果として、就労目的の学生を受け入れる営利目的の日本語学校の乱立を招いた。背景には、バブル経済期の人手不足を補う労働力のニーズがあり、このころから、偽装留学生が増えていく。
90年代に入ると、政府は日本語学校の認定制を導入、留学生ビザ認定審査を厳格化するなどの措置を講じ、著しく入学者の数が減少して閉鎖・廃校に追い込まれる学校もあった。03年、計画開始から20年を経て、外国人留学生の総数10万人の目標を達成。そのうち約7万人は中国籍で、その後も現在まで国籍別で最多を占める。
2008年、少子高齢化の進む日本で優秀な人材を獲得する戦略として政府が「留学生受け入れ30万人計画」を策定したことで、日本語学校は再び増えていく。留学生ビザ発給基準が緩み、就労目的の偽装留学生が改めて問題視されるようになった。
中国資本の参入
安定かつ継続した学習環境を担保する意味合いから、90年代以降、日本語学校の認定には、校地や校舎は賃貸ではなく「自己所有」であることが原則とされた。
この基準がきっかけで、日本語学校を手放す経営者もいた。当時の状況に詳しい元日本語学校管理職は、「この局面で中国資本による買収が起こった。『自己所有』は経営者にとって負担増となり、逆に不動産投資を得意とする中国資本にとっては商機となった可能性があります」と話す。
確かに取材を進めるにつれ、国内の日本語学校には中国資本や韓国資本など、外国資本が少なくないことが分かった。「10万人計画」当初、留学生として来日した中国人や韓国人が、日本語学校の経営に乗り出したケースもあるようだ。特に中国資本が目立つのは、中国籍の留学生が最多であることも一因だろう。
また業界内では、近年進行した留学生の多国籍化、中国人の高学歴取得のニーズなど、トレンドの変化に対応できない日本語学校が増えて、「中国資本による新たな買収局面を生んでいる」との見方もある。法務省では外国資本の学校数を把握していないため、中国資本の正確な数は不明だ。前述の元日本語学校管理職は、「あくまでも推測ですが、告示校のうち中国資本は3分の1近くあるのでは」と話す。
日本語学校経営のもう一つの障壁は、「仲介料」の存在だ。ある外国人材コンサルタントは、「東日本大震災や翌年の(尖閣列島国有化に抗議する)反日デモ以降、中国人留学生確保が困難になり、現地仲介業者の手数料が学費の20パーセントを超えるようになった」と話す。
日本語学校への留学生募集は、現地の教育機関との提携や海外各国の仲介業者から紹介を受けるのが通例だ。後者の場合、斡旋業者に支払う仲介手数料に経営が大きく左右される弱点がある。優秀な学生を獲得するために学校関係者が現地を視察したり、駐在したりする必要も生じる。
長年日本語教育に携わってきた大東文化大学名誉教授の田中寛(ひろし)氏は、留学生確保の難しさについて、こう振り返る。「(大東文化大を含め)日本の一部の大学も留学生を招致するために、海外都市部に拠点を設けて日本人職員を常駐させました。経営的に割が合わず、多くが撤退したようで、効率はよくなかったと思います」
外国資本化によって日本語学校は現地のコネクションを活用でき、仲介業者との間に言葉の壁がなくなるので現地駐在スタッフの必要もないなど、留学生募集関連の経費削減につながるという側面もあるのだ。
冷遇される日本語教師
日本語教師は「食べていけない」職業だといわれる。良心的な教育で知られる都内のある日本語学校を取材すると、教師たちが授業やさまざまな教務に追われていた。日々、学生の遅刻・欠席の管理をしつつ授業態度の改善を促し、宿題で理解を確認するなど、細かいフォローを行っている。仕事にはやりがいを感じているが、「授業1コマあたりの単価の安さ」が不満・不安の種だという。
他方、都内の中国資本の日本語学校に勤務するある教員は、「コマ給が日本資本の学校より高く、教案の提出などを求められることもないので、教員の負担は少ない」と話す。留学生への指導体制や校舎の衛生面などに気になる点はあるが、「細かいことには目をつむっている」そうだ。
筆者の調べでは、都内の日本語学校の1コマ当たりの単価は、1800円程度が相場。中国資本の場合、1コマ2000~3000円のようだ。
中国の大手商社出身で日中の企業文化に詳しい森山大道(だいどう)氏は、ビジネスとしての日本語教育に関心を寄せ、こう指摘する。「日本語学校の経営は、真面目に細かくやるほど非常にコストがかかります。一部の中国資本はそれを大胆に省けるからこの業界でも生き残ることができるのです」
だが、効率を優先することで、多様化している学生のニーズに応じた指導や、日々の細かいフォローがおろそかになってしまうのではないか―そんな懸念は否めない。
日本語教育のゆがみ
これまで、政府が推し進めてきた留学生拡大の施策に対して、日本語学校を中心とする受け入れ態勢の整備は遅れを取ってきた。偽装留学生を排し、教育の質向上を実現するには、日本語教育機関認定法の下で、どれだけ悪質な学校が淘汰されるかがカギになる。
だが、それだけでは解決しない。文科省は専任教師の配置基準を「生徒60人につき1人」から「40人に1人」に引き上げた。在留外国人の数も増え、日本語教師の需要が高まる中で人材を確保するには、安定した雇用と給与面での待遇改善が必須だ。日本語学校の教師は大半が非常勤だ。国家資格を取得しても、待遇が現状のままなら、若い人材は定着しないだろう。
教師の給与が低いのは、仲介手数料など留学生募集コストを捻出するために、人件費を安く抑えているからだとの見方もある。認定法では、仲介手数料の適正化を求めているが、明確な基準は示していない。
留学生を増やす目標を掲げても、政府は日本語学校を助成対象とはみなしてこなかった。学校経営は授業料だけでは厳しく、仲介手数料のコストやパンデミックなど不測の事態に大きく左右される。
文科省は、認定校を対象に民間企業や自治体、大学などから教育投資を促す仕組みの構築を目指している。企業や自治体との連携を通じて、日本語学校の脆弱(ぜいじゃく)な経営基盤を強化し、教師の待遇改善を実現する。産業界は「育成就労」「特定技能」の仕組みを通じて人手不足に対応する。こうした環境が整ってこそ、知日派や外国人材の育成にもつながるのではないだろうか。
【参考サイト】
バナー写真:PIXTA
