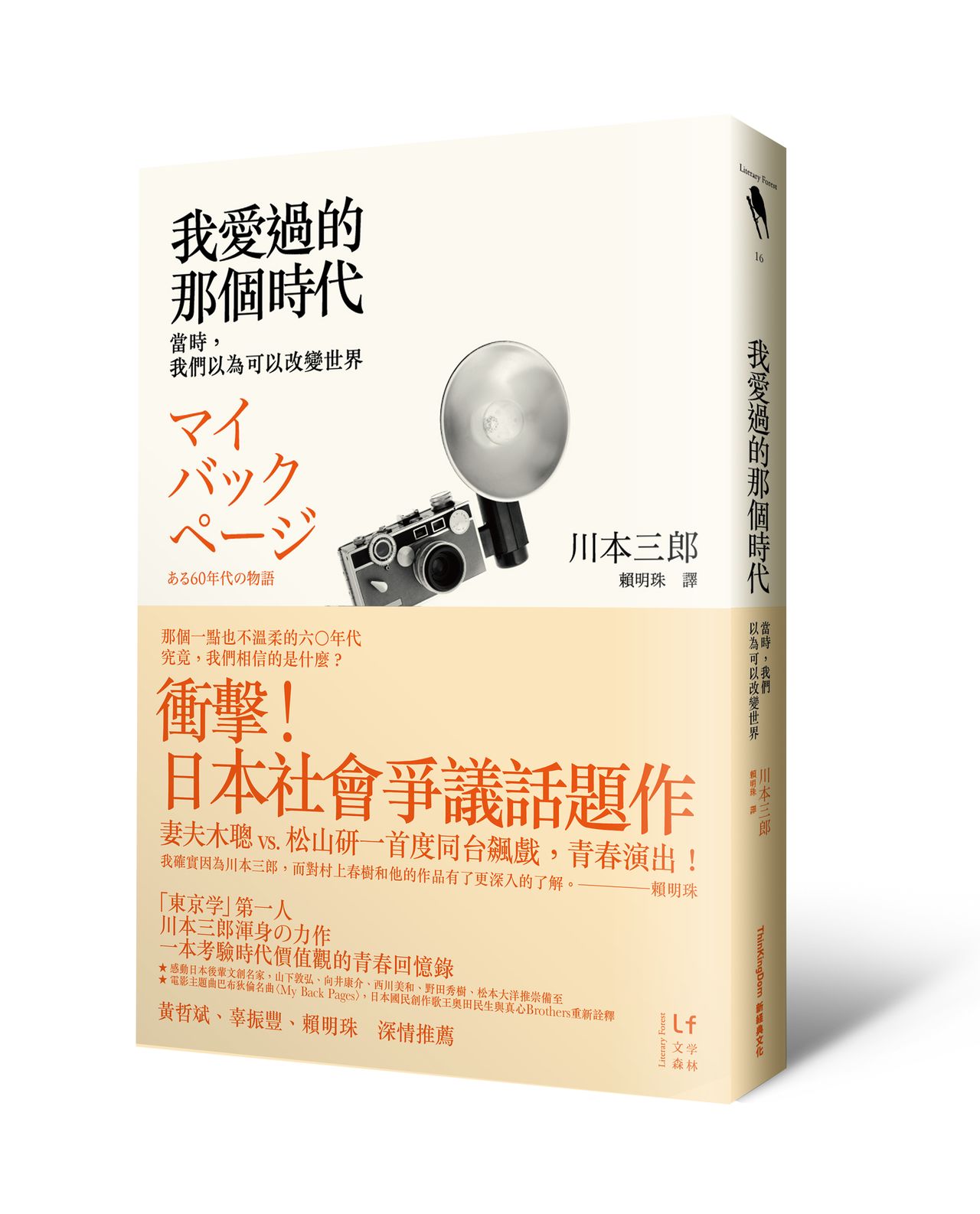日本の評論家の著作が外国語に翻訳されることは滅多にない。しかしながら、川本三郎の作品は台湾で5冊も翻訳されている。なぜ、それほどまでに川本作品は台湾で支持されているのか?
ヒマワリ学生運動のために何か一言を
2015年3月、台北の誠品書店・信義店で聞文堂、聯経出版、文化部(日本の文化庁に相当)の合同で日台作家による対談イベントが開催された。イベントのトリを飾ったのは川本三郎氏と李明璁氏の「文学、歴史、映画における東京散歩」だ。
14年に起きたヒマワリ学生運動から1年経った当時、台湾で出版されていた川本氏の著作は、学生運動が盛んだった60年代を舞台にした回想録『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』の翻訳版『我愛過的那個時代(11年)』の1冊のみだった。「東京学」の第一人者である川本氏だが、台湾ではこの15年のイベントまで映画『マイ・バック・ページ』(2011年公開)の原作者で、劇中で妻夫木聡さんが演じた記者のモデルとなった人物という印象の方が強かった。
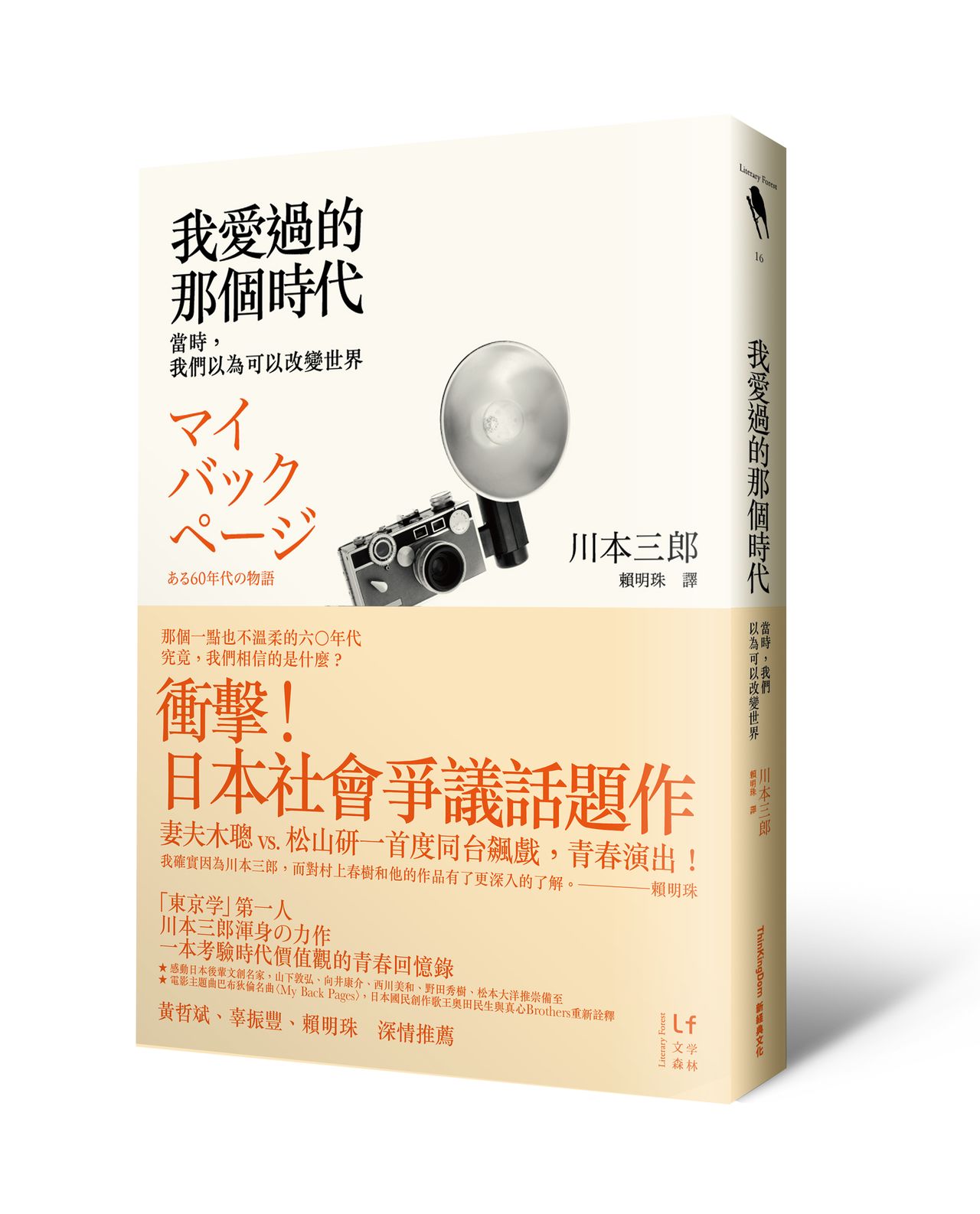
台湾の学生運動世代の共感を引き起こした『マイ・バック・ページ』の翻訳版『我愛過的那個時代』
川本氏と対談した李明璁氏は台湾の学生運動の積極的な支持者だ。2008年に起こった馬英九政権の対中政策や集会規制に対する抗議運動である「野イチゴ学生運動」では、李明璁氏は学生と手を携えて警察に立ち向かった。野イチゴ学生運動に参加した“子供”たちが数年後にヒマワリ学生運動の中心人物になった。
そのヒマワリ学生運動の時期、私はネットでこんな書き込みに目を止めたことがある。立法院に座り込みをした学生、そして立法院の外の青島東路で待機していた学生たちが川本三郎氏の『マイ・バック・ページ』のこの一節を引用し、ネットに投稿していたのだ。
「あの時代は象徴的にいえばいつも雨が降っていた。時代は少しも優しくなかった」
ヒマワリ学生運動の仲間たちの間で川本氏が話題になった時、台北はちょうど雨の多い初春を迎えていた。
ヒマワリ学生運動の撤退から1年後、私は誠品書店で日台の学生運動と密接な関係がある2人の話を聴いていた。イベントは東京散歩の話で盛り上がる一方、私は物足りなさを感じていた。対談が終わり、質疑応答のコーナーになったとき、思い切って手を挙げた。今、川本氏にヒマワリ学生運動について聞かなければ、彼は日本へ帰ってしまう! そんな焦りから、質問した時、私は激しく震えていたように思う。
「ヒマワリ学生運動に参加したあの時の子供たちに、何か一言いただけませんか?」
川本氏は「自分は先輩でもなんでもない、たまたまその時代のあの場所にいただけ」と謙遜し、学生らに、たとえ要求が完全に受け入れられなくても失望することはない、あの時の努力は、その後の人生でいつか生きてくる、と伝えてくれた。
壇上にいた川本氏と李明璁氏は同時に背筋を伸ばし、そしてその瞳はキラリと輝いた。その瞬間は今でも忘れがたい光景である。
川本三郎がいて、村上春樹を知った
川本三郎氏の作品を初めて台湾で翻訳した出版社は、新経典文化(Thinkingdom Media)だ。同社は台湾でまだ知られていない日本人作家をヒットさせることに長けた出版社だ。たとえば『深夜食堂』の作者である安倍夜郎氏、『神去なあなあ日常』の三浦しをん氏、最近だとお笑い芸人の矢部太郎氏による漫画『大家さんと僕』が挙げられる。
新経典文化の編集主任を務める葉美瑤氏は、同社設立前は時報出版で10年以上にわたり、村上春樹作品の刊行に携わってきた。葉氏の川本三郎氏との出会いも、村上春樹氏と関係がある。きっかけは翻訳者の賴明珠氏(※1)がある雑誌編集者から、村上春樹氏の小説を紹介する記事の寄稿を依頼されたことだった。
日本では川本三郎氏が「村上春樹は新文学の旗手である」と評価していた。そこで賴明珠氏は川本氏の言葉を引用して村上氏の小説の一部を翻訳し、紹介したという。川本氏の評論がきっかけで台湾は村上春樹氏を知るようになったのだ。
葉美瑤氏は川本氏の第一印象をこう語る。
「学生運動家が起こした事件に関与したために、記者の身分を失った(朝日新聞社を懲戒解雇)川本先生は、その後何でも書ける評論家を目指して、大量の本を読み、大量の映画を観たと言います。川本先生は最も早く村上春樹の才能に気づいた人物です。村上春樹が小説で新人文学賞を取った時、一部では『こんな小説を読む読者はいるのか』と思われていましたが、川本先生は新時代が来たと直感したそうです。台湾の村上春樹ファンは川本先生に感謝しています。川本先生がいたからこそ、私達は村上春樹知ることができたのです」
さらに、新経典文化が川本氏に関心を持ったのにはこんな理由もあった。
「出版社ができて1年目に作った3冊目の本が、馬世芳(※2)の『My Back Pages(昨日書)』でした。タイトルは元々ボブ・ディランの曲にちなんだものなのですが、私たちはその後、ネット上で川本先生も同名の『マイ・バック・ページ』という同名の著書があり、さらに映画化されることを知りました。そして内容を調べて、本当に驚きました。なぜなら私達がずっと待ち望んでいた本だったからです」
それは『ノルウェイの森』の理解を深めるものになると感じたからだという。
「私達は村上春樹の『ノルウェイの森』を読み、面白いと思いました。しかし、私達には三島由紀夫の切腹も全共闘も同時代での目撃体験はありません。1969年は私達が生まれて間もない頃です。この時代の日本の学生運動のことはなんとなく知ってはいますが、実際に何が起きていたのか、はっきりとは知らないのです。私は川本先生が著書の中であの時代を語っていることに気づき、これは『ノルウェイの森』ファンを救うものいなると直感しました。(時代背景が分からなければ)『ノルウェイの森』はただの複雑な愛情関係の物語になってしまう。しかし川本氏の本を読めば、『ノルウェイの森』の愛情関係はただの愛情ではないことがわかる。『マイ・バック・ページ』こそがあの時代を確かにとらえているものだと感じたのです」
編集部は『マイ・バック・ページ』の翻訳版のタイトルを本文から引用することにした。そして台湾版のタイトルが『我愛過的那個時代(私が愛したあの時代)」に決まったのだ。
「このタイトルは多くの人の心に響きました。後から分かったことですが、台湾人読者にとってもこの感覚は理解しやすかったのです。それは誰でも持っている、春だったり、忘れがたいもの、過去に受けた傷…など、それらはあの時代を生きた人達と同じなのです」
(※1) ^ 賴明珠:台湾の日本語翻訳家。多くの村上春樹氏の小説の翻訳を手がけ「村上春樹の中国語翻訳の担当者」と呼ばれるほどである。川本三郎氏『マイ・バック・ページ(我愛過的那個時代)』の翻訳も担当。賴氏はこの20年来、村上春樹氏の文体、独特の作風と雰囲気、そして時代の感覚をつかむことができたのは川本三郎氏のおかげだとしている。
(※2) ^ 馬世芳:台湾人作家、ラジオパーソナリティ、音楽評論家。母親は「台湾の民謡の母」として知られるラジオパーソナリティの陶暁清。
『マイ・バック・ページ』は読めば読むほど味わい深い一冊
一般的には、台湾人が日本人作家にコンタクトを取ろうとすれば、恐らく多くの人を介する必要があるだろう。しかしマネージャーを持たない川本氏は直接、台湾の編集者と直筆の手紙でやり取りをするのだ。
葉氏は「私達が川本先生を台湾に招待することもありますが、先生がご自身でいらっしゃることもあります。しかも先生は出版社に対して宣伝イベントの開催なども要求しません。『川本先生、あなたは本当に日本人ですか?』と思ってしまうくらいです。後から思い返すと、確かに川本先生は普通ではありません。20代で職を失い、その後、どこかに所属することもありませんでした。つまり体制の外の人なのです。それが年齢の差を感じさせなくしているのでしょう。川本先生を見ていると私は『男はつらいよ』の主題歌を歌いたくなります」と話す。
さらに、「川本先生には人をひきつけるものがあると思います。まだ評価されていなかった村上春樹を論じたように、川本先生の心は広く、偏見がありません。日本人作家は往々にして守られている印象を受けますが、川本先生はとてもオープンです。お年を召されていても川本先生が台湾で関心を寄せるものは少しも古くありません。私達が知らないものさえあるくらいです」と、印象を語った。
また葉美瑤氏は川本氏が描く旅には生活感があると話す。日常の延長のような旅行であれ、もしくは一見、孤独な個人旅行であっても、川本氏の手にかかれば、味わい深い生活感が醸し出されるのだ。
「正直言って、『マイ・バック・ページ』に描かれた川本先生は完全に『社会に対し、憤る若者』だと思います。あの時代が過ぎた今、こんなに魅力的で、私達が見たことがないような日本の姿を見せてくれる70代の作家としての川本先生と出会えることになるなんて、思いもよりませんでした」
現在、台湾で川本氏の著作は5冊翻訳出版されている。「どの本を一番気に入っていますか?」という問いに対し、葉美瑤氏が選んだのはやはり『マイ・バック・ページ』だった。
「日本人にとってこの本は、青春を描いた傑作だと思います。こんな風に自身の青春時代を描き出す人はそういないでしょう。川本先生は何年もあの時代について触れることができなかったところ、ついに筆をとったといいます。先生は自身が生きたあの時代と真剣に向き合ったのだと思います。川本先生は決して『過ちを犯した』とは言わないでしょう。『あの時、ああしなければよかった』とも言わないでしょう。しかしそこには懺悔(ざんげ)のような空気が存在するのです」
『マイ・バック・ページ』の位置づけについてはこう語る。
「もし学生運動を経験した川本三郎という人物に出会わなければ、彼の他の作品を読んでも、たとえば戦時中に母親が作ってくれた弁当のこと、妻の死、なつかしい料理の話を読んでも、感動はするかもしれませんが、それだけです。『マイ・バック・ページ』を読んでいれば、彼の人生の厚みを感じることができるでしょう。一見、素っ気ないような散文からも、豊かな情感を感じることができるでしょう。日本では学生運動やあさま山荘事件を描いた数々の映画や小説がありますが、どれも今ひとつはっきりしない印象がありました」
「そんな日本の学生運動の印象を塗り替えてくれたのが『マイ・バック・ページ』です。1人の人間を主軸としたこの本を読めば、まるで自分があの時代に身を置いたかのような錯覚に陥ります。事はこんな風に1つ1つ動いていた、そして多くのことが発生しては理解しきれないまま次々と変わっていく。何を信じたら良いか、わからない状態で選択を迫られたら正しい判断ができるものでしょうか」
『マイ・バック・ページ』の編集を担当した陳柏昌氏と編集主任の葉美瑤氏には10歳ほどの年の差がある。陳柏昌氏に川本氏の著作の中でどれが一番好きか尋ねたところ、陳氏も迷うことなく『マイ・バック・ページ』を挙げた。
「何と言ってもこの本は川本先生が新聞記者として、学生運動を取材していた頃を回顧した作品ですし、私個人としてもこの本が好きです。川本先生が描いたあの年代は確かにとても特別です。誰にとっても20代、30代は大切な時期ですが、先生はその頃に人生が激変するような体験をしたのです。内容も書き方も、読めば読むほど味わいが増す本だと思います。編集していた時、『川本三郎の文体』とは何かを考えていたのですが、この本がそれを確かなものにしてくれたと感じています」

野百合学生運動世代の羅文嘉夫妻が経営する「我愛你學田書店」で行われた川本三郎特別展。川本氏と羅文嘉氏の対談も行われた(台湾新経典文化提供)
川本三郎が出会った唯一の他言語の読者、台湾
葉美瑤氏によると、川本作品の台湾の読者層は日本の読者層より若く、日本への思い入れがある読者であればあるほど、川本作品を面白いと感じる傾向にあるという。
「出版社の立場からすると、川本三郎という作家はすぐに売れはしないかもしれませんが、面白いものをたくさん持った人物だと思います。私は川本先生の作品を読んで『男はつらいよ』を観始めました」
新型コロナウイルスの流行前、川本氏は雑誌「東京人」、新潮社の編集者と聞文堂の黄碧君と共に定期的に台湾を訪れては、川本氏が好きな台湾映画の「聖地巡礼」をしていたそうだ。また、何度か小規模書店によるセミナーに登壇したこともある。これが川本氏にとって最も慣れた読者との交流の方法だ。2019年末に屏東で行われた大型イベント「南国漫読節」のステージでは、川本氏は緊張しっぱなしだったという。

2019年の屏東で開催された「南国漫読節」での対談をする川本氏と李明璁氏(台湾新経典文化提供)
葉美瑤氏は川本氏は台湾に特別な感情を抱いていると感じている。
「川本先生の作品は他の国や他の言語では翻訳されていません。川本作品が出会った他言語の読者は台湾だけなのです。数字だけを気にする出版社や作家もいますが、川本先生は別のところを気にかけてくれます。たとえばみんなと育んだ友情です。きっとそんな川本先生のふるまいが、彼を『外国人作家』と思わせない、私達の仲間だと思わせてくれるのだと思います」
バナー写真=台北・大稻埕「青鳥居所書店」で映画『男はつらいよ』を語る川本三郎氏(台湾新経典文化提供)