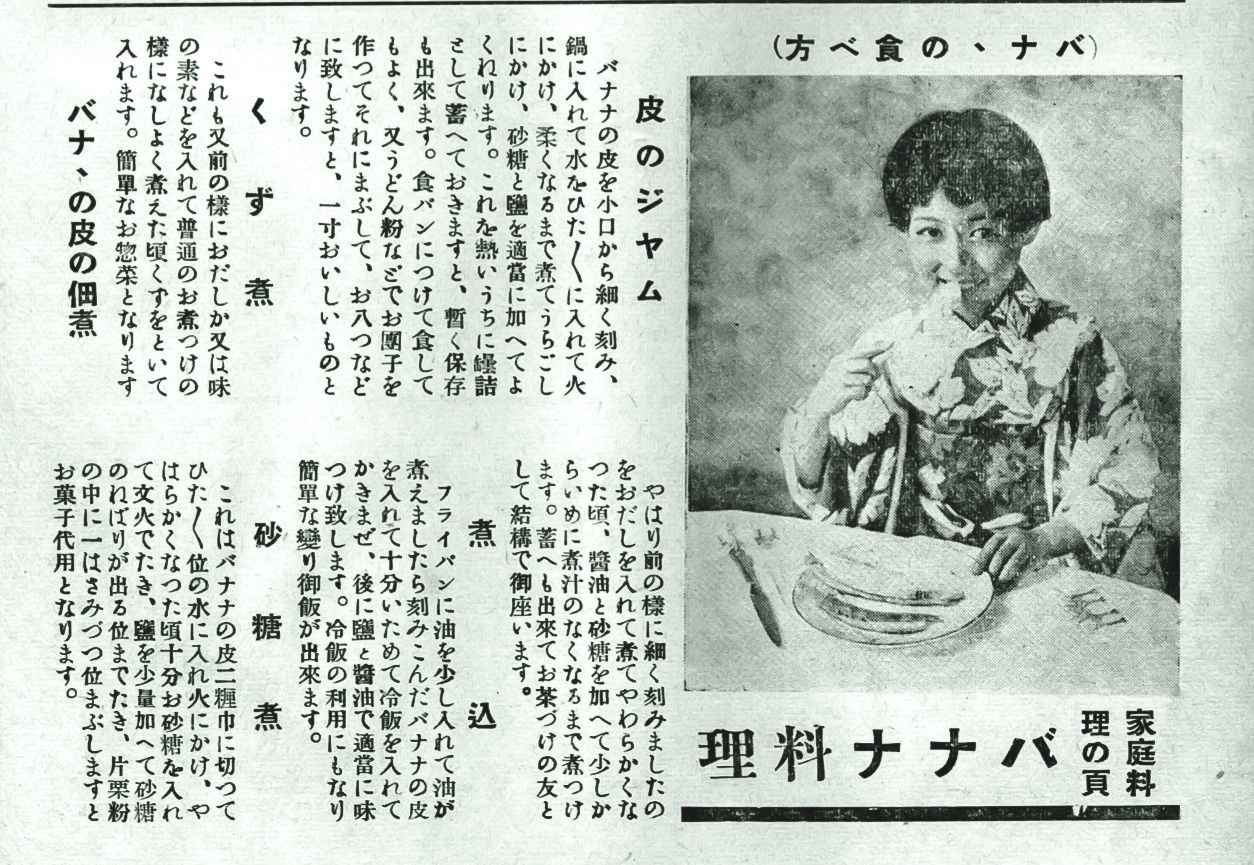日本人が一番食べている果物
新型コロナウイルスの影響を受けていない業界は皆無だが、バナナも例外ではないらしい。輸入バナナの大半を占めるフィリピン産は同国のロックダウンの影響で出荷や梱包に支障が出ている上に、輸入第2位のエクアドルも出荷を自粛したため、今年はバナナの輸入が大幅に減少しそうだという。
日本人は一世帯あたり年間18.4キログラム(2018年総務省家計調査、2人以上世帯)のバナナを購入している。食卓でおなじみの果物であるリンゴやミカンは2000年以降、購入量が大幅に減っているが、バナナの消費は衰えていない。

実は、日本人がバナナ好きになった原点には、台湾のバナナがある。1970年になってエクアドル産バナナが台湾産の輸入量を上回るまで、日本人にとって「バナナといえば台湾」だった。

「台湾青果株式会社」が作成したバナナの広告(筆者提供)
台湾バナナをめぐる攻防戦、台湾総督府vs〈内地〉のバナナ問屋
2019年は、タビオカミルクティーが空前の大ブームとなった。その前には、パイナップルケーキやマンゴーかき氷が人気となるなど、台湾スイーツは日本人の好みに合うようだ。しかし、日本人が最初に魅了された、台湾の甘いものと言えば、台湾バナナだ。
台湾バナナが日本で食べられるようになったのは20世紀の初頭。最初は、台湾と日本を行き来する船の船員がごく少量を持ち込み、港周辺の商店などで販売されていたという。商業ベースに乗せたのは、大阪商船会社基隆支店の都島金次郎という人物らしい。1903年8月27日に基隆港から出航する恒春丸に和尚洲(現在の蘆洲)で採れたバナナ約400キロを積み、神戸まで移送したという。

台中の台湾バナナ市場(Lafayette College Libraries, East Asia Image Collection)
その後、日本のバナナ消費は増え続けた。1924年12月には台湾各地の青果物同業組合を統合した台湾青果株式会社が、翌年2月には東京・横浜・大阪・神戸・下関・門司に台湾青果荷受組合が設立された。この2つの組織が設立されたことで、台湾から日本にバナナを移出する安定した環境が整えられたといえる。
こうして台湾の主要輸出農産品となったバナナだが、バナナ熱が高まる<内地>は、必ずしも台湾青果株式会社の設立を歓迎したわけではなかった。なぜならば、台湾バナナは高級品だったからである。1925年7月8日の読売新聞朝刊には、「高いバナナを食わされる内地人 台湾からの移入が全部一会社の手に独占され」との見出しが躍る。
日本のバナナ問屋の中には、台湾青果を通さず、生産者と直接取引を希望する「反台湾青果」派がいた。同記事は、反対派が直接取引をしたバナナを船に積もうとしたところ、台湾総督府に阻まれ、岸壁に積み上げられた480籠(ひと籠は約37〜41キロ)のバナナは腐るのを待つばかりになっていると訴える。バナナ熱の高まりの背景には、バナナでもうけたい台湾総督府とバナナを安く買いたい〈内地〉の攻防があったわけだが、1920年代後半には年間一人36本消費する計算になるほど台湾バナナは〈内地〉の食卓に入り込んでいった。

台中のバナナ市場(Lafayette College Libraries, East Asia Image Collection)
皮まで食べたい!? ジャムや寒天寄せなどレシピいろいろ
なぜ日本人はこんなにも台湾バナナに魅了されたのだろうか。もちろん、最も大きな理由は、台湾のバナナがおいしいから!に尽きる訳だが。日本人にとって高級なフルーツであったバナナは、「文化的生活」の象徴でもあった。そう、バナナは文化的な食べ物だったのである。
『実業時代』(1929年10月)には、「文化的民衆的となって国民生活上なくてはならぬ食料品バナナが日本人の口に入るまで」という記事が載ったり、『熱帯園芸』(1937年12月)にはバナナの消費が都会に偏っているのは「文化生活が(バナナの消費を)然らしめている」からだという消費傾向の分析が載ったりしている。
1920〜30年代の雑誌には、そんな文化的な食べ物であるバナナを余すところなく味わうためのレシピがさまざま紹介されている。中でも、「え、そこまで食べるの?」と目を引くのがバナナの皮を使ったレシピだ。
美味しいバナナの皮 捨てないで煮て食べませう
バナナの皮はその辺に投げてありますとそれを踏んですべったり、腐りかけると蝿がとまってきたないものですが、これを薄く切って砂糖と塩を加えて十分乃至(ないし)二十分位煮ますと柔かくなりますから、これを冷まして食べますと大変おいしいものです。(『婦人と家庭』1920年10月)
赤塚不二夫の漫画でもおなじみのバナナギャグからはじまるこのレシピは、大真面目においしい食べ方としてバナナの皮のジャム(のようなもの)を紹介している。バナナの皮を食べることが一般的だったわけではないだろうが、『台湾芸術新報』(1935年9月)にも「皮のジャム」にはじまり、「くず煮」「バナナの皮の佃煮」などバナナの皮を満喫するレシピが載っているし、読売新聞の1926年6月5日朝刊にもバナナの皮の寒天よせが紹介されている。バナナ好きを通り超して、もはやバナナ狂の感さえある。
昭和のバナナ熱に当てられたのか、近所の八百屋さんでバナナを手に取った私は、バナナの皮のジャムを作ってみることにした。『台湾芸術新報』掲載の、少し上品なレシピを選んだ。バナナの皮を細かく刻み、ひたひたの水で柔らかくなるまで煮る。柔らかくなったら、裏ごしし、砂糖と塩を適当に加えてよくねって出来上がり。結論から言うと、香りという香りはないのに、妙に生々しいざらざらした舌触りのお世辞にもおいしいとは言い難いものが出来てしまった。皮を煮る時間が少なかったのか、こし器の目が粗かったのか、それともやはり台湾バナナではなかったからなのか…。
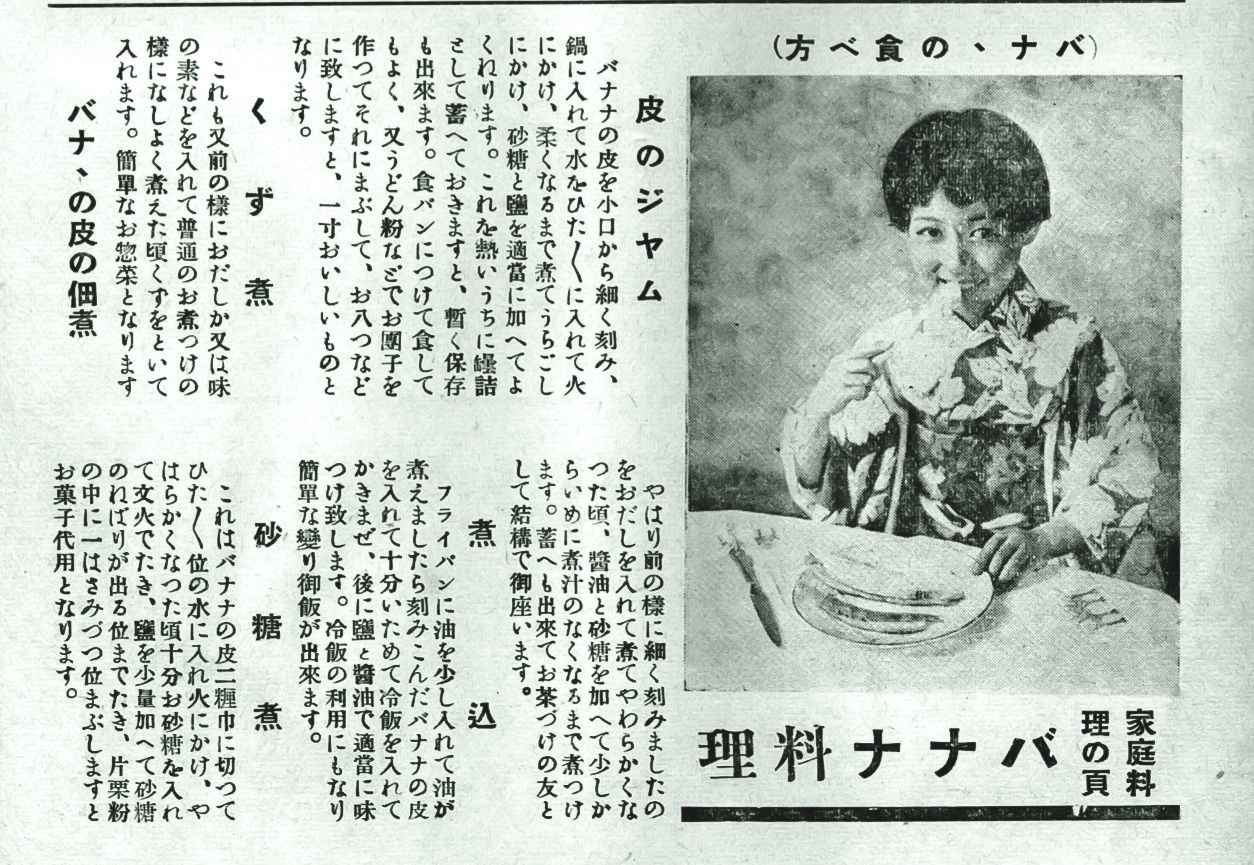
バナナに関する各種レシピを紹介(『台湾芸術新報』(1935年9月))
台湾バナナのシェアはわずか0.2%に
昭和を代表する人気作家の一人である獅子文六は、1959年2月から、読売新聞で新聞小説『バナナ』の連載を始めるにあたってこんなことを言っている。「バナナは日本でならない果物なのに、日本人はバナナ好きで、バナナなしに生きられない様子である」。
バナナといえばまだ台湾バナナだったころの小説である。ちなみに、獅子文六の視界からは漏れ落ちているが、実は、戦前から小笠原と沖縄は国内のバナナ産地として認識されていた。ただ、やはり、台湾バナナの方が味がいいという声がよく聞かれたようだ。
主人公は台湾生まれの在日華僑・呉天童で、息子の龍馬がバナナ輸入業に手を出したことをきっかけにてんやわんやの大騒ぎになっていく。主人公が台湾華僑であることや、龍馬がバナナ貿易でひともうけしようとたくらんだことには、戦後日本の社会情勢が関わっている。
戦後初めてのバナナ輸入は、在日米軍へ納入するために台湾華僑を介して行われたと言われている。在日米軍への納入を皮切りに、1950年には台湾バナナの輸入が正式に再開された。63年に輸入自由化されるまでの13年間、「バナナなしには生きられない」日本人にとってはつらいことに、台湾バナナは庶民の手が届かない高級品として君臨した。
バナナといえばフィリピン産の現在、輸入バナナのうち、台湾産が占める割合はわずか0.2%である。台湾バナナはまた少し高級なフルーツになった。スーパーでたまに見掛けると、値段を見て買うのをちゅうちょすることもあったが、今度見掛けたら日本人をバナナ狂たらしめた台湾バナナで「皮ジャム」のリベンジを果たしたい。
バナー写真=筆者自ら作ってみたバナナの「皮ジャム」(筆者撮影)