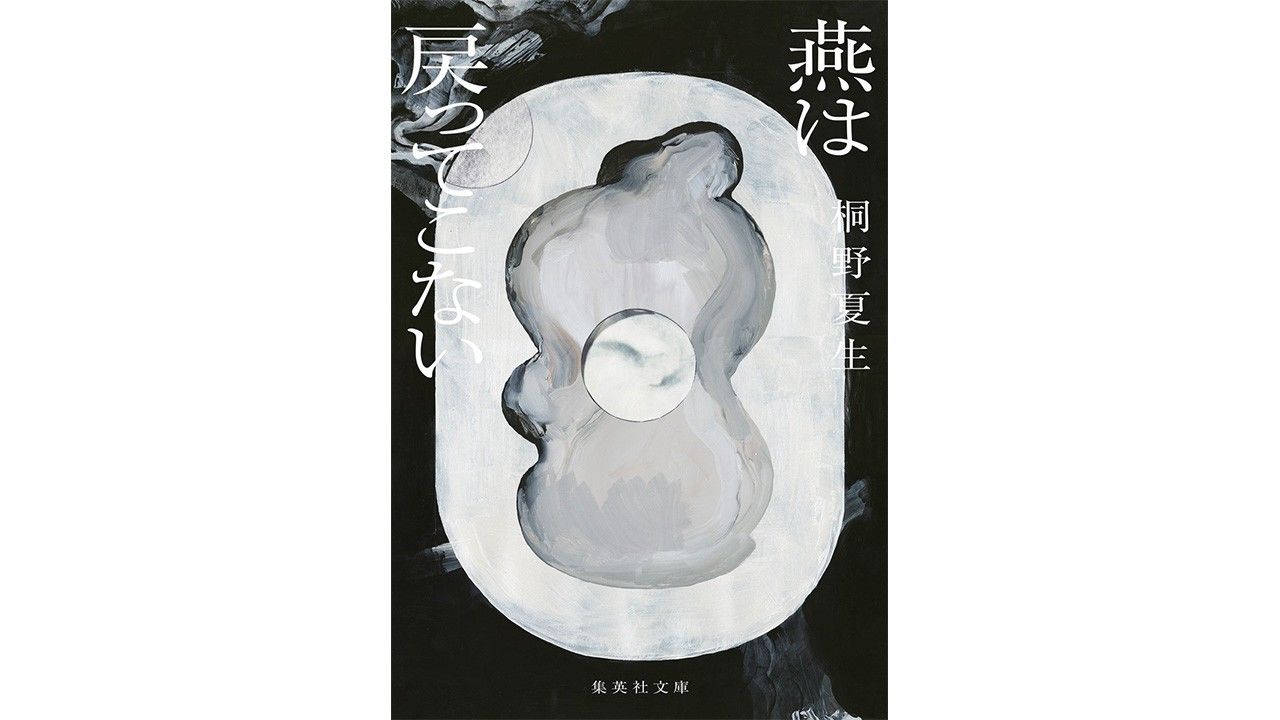
【書評】正しさとはいったい何か:桐野夏生著『燕は戻ってこない』
Books 家族・家庭 健康・医療- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
こんな結末を用意していたのか。
それが、読み終えた直後の感想だ。と同時に、どっぷり浸かっていた物語の世界から突然解き放たれたようで、ふうっと大きく息をついた。
本書のテーマは代理出産。
不妊に悩む夫婦の選択肢の一つで、母親以外の女性の子宮に受精卵を戻して胎児を育て、出産後、依頼した夫婦が子どもを引き取る。アメリカでは1980年代から一部の州で合法的に行われ、市場としても年々拡大。2022年には世界中で140億ドル、2032年には1290億ドルに成長すると予測されている。
日本では認められていないため、子どもが欲しい日本人の夫婦が、アメリカやウクライナなど外国に渡航して代理出産を行うケースが増えているそうだ。
誰がヒロインで誰が悪役なのか
主人公の草桶夫妻も長年不妊治療を行ってきたが子どもを授かることができず、妻の悠子の卵子が老化していること、さらに不育症(妊娠しても流産や死産になる可能性が高く、胎児を子宮内で育てることが難しい)との診断もあり、夫の精子と代理母の卵子を使った代理出産をエージェントに依頼する。
両親とも日本人のDNAを持った子どもを望む二人は、日本人の代理母を希望──つまり違法行為であり、彼らはそこに大金を支払う準備もできている。
この代理母を引き受けるのが、もう一人の主人公リキだ。北海道から上京し、派遣社員として働きながら、毎月82000円の予算でギリギリの暮らしをしている29歳のリキにとって、1000万円という謝礼は見たこともない大金であり、この依頼は人生を変える魅力的なチャンスに映る。
依頼主の悠子、代理母のリキという2人の女性に加え、悠子の親友やリキの友人、そして悠子の義母など、さまざまな“女”が登場し、それぞれの立場から今回のできごとに関わってきて、物語は緩やかに動き始める。
この女性たちの人物描写が、とにかくうまい。
裕福と貧困とか、産める人と産めない人、という分かりやすい二分法に配置するのではなく、それぞれの立場が場面ごとにくるりくるりと入れ替わっていり、誰がヒロインで誰が悪役なのか分からなくなる。
さらに読み手自身の生い立ちや置かれている状況、読んでいる瞬間の感情が掛け合わされ、若い頃の自分を思い出してリキに共感して悠子の勝手な言い分に憤ったら、次の瞬間には母親の目線からリキの自分勝手さが許せなくなって悠子に同情する。気が付けばどっぷりストーリーに浸かっていて、この物語の行きつく先が知りたくてたまらなくなっている。
ラストシーンをどう受け止めるか
主婦4人と殺人をテーマにした『OUT』、女性の中に渦巻く様々な感情を扱った『グロテスク』など、桐野作品には女性を真ん中に据えた、生々しく骨太な物語が多い。
小説なのにまるで自分のことが描かれているようなリアリティがあるのは、登場人物の誰もが負の側面を持っていて、まるで呼応するように、読者もまた自分の中にある本音や負の感情に気が付かされてしまうから。それが桐野作品の“怖さ”でもある。よそ行きにきれいごとで塗り固めようとしても、グイグイとその衣装を引き剝がされてしまうのだ。
本書でもそれは同じだ。今回は、ある年齢以上の女性ならおそらく誰でも考えたことがある、結婚や妊娠、出産に対する自分の価値観や葛藤、さらには富に対する本質的な憧れや、貧困から逃れたいという必死さ、愛されたいと願う哀しさなど、生々しく複雑な感情が、登場する女性たちの言葉に巧妙に散りばめられ、まるで鏡のように、読者自身を照らし返してくる。
代理母を引き受けたリキの物語は、彼女が双子を妊娠したことで、さらに大きく変化していく。それは、ここまで無意識に受け身で生きてきたリキ自身の覚醒のプロセスともいえるのだが、小さな小さな男の子と女の子の母となった彼女は、草桶夫妻と交わした代理母の契約書を前に、どう行動したのか。
それが物語のクライマックスであり、タイトルを象徴する場面にもなっている。
リキの決断に快哉を叫ぶ人もいれば、怒りを感じる人もいるだろう。涙する人もいるかもしれない。100人の読者がいれば、100通りの感想が飛び出すような気がする。数年後に読み返したら、また、まったく異なる感情を抱きそうだ。
自分がリキなら、どうするのか──。その答えを知ることは、自分の人生そのものを見せつけられること。ちょっと怖くもあるが、ぜひ覚悟を持ってこの極上の小説を楽しんでほしい。


