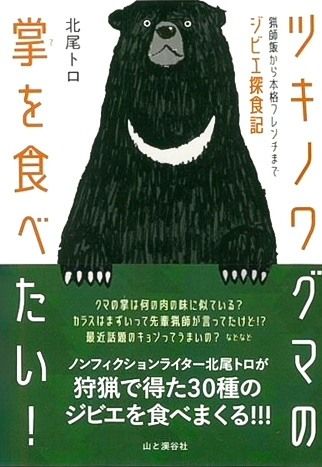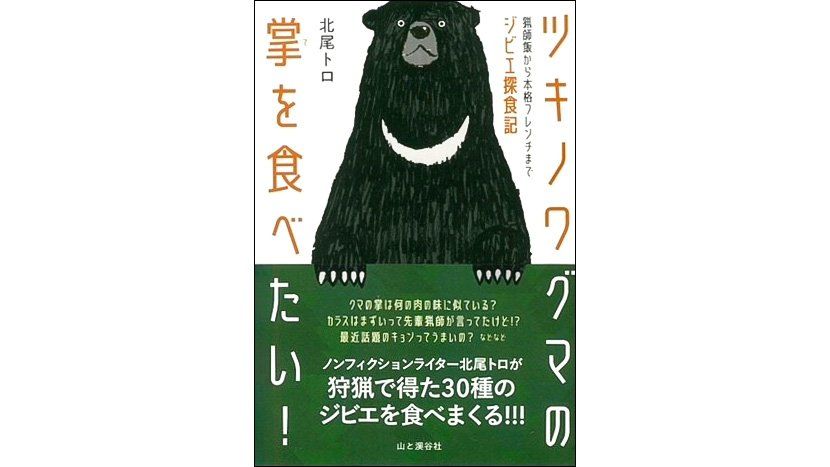
【書評】和風ジビエの魅力と最新事情:北尾トロ著『ツキノワグマの掌(て)を食べたい!』
Books 食 環境・自然・生物 文化- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ハンター作家のジビエ食べまくり
「ジビエ(gibier)」はもともとフランス語で、狩猟によって捕獲された野生鳥獣やその肉のこと。欧州では貴族の伝統料理として発展してきた歴史がある。日本でも東北地方山間部の狩人(かりうど)「マタギ」など古くから狩猟文化があった。
著者、北尾トロ氏は1958年、福岡県生まれ。狩猟免許を持つノンフィクション作家だ。第一種銃猟免許を取得したのは2013年。ハンター・ライターとして「ジビエの食べまくり」に挑戦してきた。
狩猟鳥の“最高峰”といわれるヤマドリをはじめ、キジ、マガモ、ハシブトカラス、キジバト、カワウ、エゾライチョウ……。獣類では定番のシカやイノシシに加え、タヌキ、キツネ、ハクビシン、アライグマ、ノウサギなど。ときには自ら解体・調理し、鳥獣合わせて30種を味わい尽くした。その記録をカラー写真とともに本書に盛り込んだ。
ハンターシェフの料理店を紹介
「朝は空気銃で鳥を撃ち、夜はフレンチ料理店のシェフになる」──。本書ではこんな見出しで、長野県松本市の「レストロリン(RESTRO RIN)」を経営する小林昌和さんを紹介している。彼は「ハンターシェフ」であり、次のような生活パターンだ。
6時前に起床して7時には現場へ。9時過ぎまで猟をしていったん帰宅。朝食後すぐ店に行き、ランチの仕込み。午後の休憩時間は店で少し休むだけで夕方の仕込みにかかる。営業を終えて店内を掃除し、家に帰るのが24時ころ。就寝は午前2時だという。そんなハードな日々を送りながら、定休日まで出猟するのだからクレイジーだ。
日本では最近、ジビエを取り扱う料理店などが増えている。本書には「樂樂」(大分県玖珠郡九重町)、「肉のスズキヤ」(長野県飯田市)などが登場する。
料理と食の本の出版社、旭屋出版から『シェフと美食家のためのジビエガイド』(監修:ワイルドライフ・ジビエマルシェ)が2024年4月2日に発行されたことも、料理店の急増を象徴している。同書には「20年以上ジビエを扱っていた老舗レストランと、ここ5年で急激に勢力を伸ばしているジビエ専門店」など新旧の全国147店を掲載している。都内や千葉県のハンターシェフの名店も含まれている。
本書では取り上げていない隠れ家的な和風ジビエの老舗もある。評者が訪れたことがあるのは「鷹匠壽」(東京都台東区雷門)、「柳家」(岐阜県瑞浪市)など。なかでもユニークなのは、猟犬も飼っている“ハンター料理人”夫婦が営む割烹「山鳥」(名古屋市西区)だ。

割烹「山鳥」の服部修、万知子夫妻はふたりとも狩猟免許を持ち、狩猟期間(毎年11月15日~翌年2月15日)には愛知県外にも遠征する(2024年4月10日、名古屋市西区)=泉宣道撮影
中国宮廷料理「熊の掌」も味わう
本書のハイライトは、いわゆる「熊の掌」だ。清朝時代の中国の宮廷料理で、満州族と漢民族の料理の粋を集めた「満漢全席」の高級メニューとして知られる。
料理したのは、著者の鳥撃ちの師匠でもある長野市内のラーメン屋「八珍」の主人、宮澤幸男さん。若いころから料理の修行を重ね、狩猟歴は40年超、「信州ジビエマイスター」でもある。ツキノワグマを仕留めた猟師から入手した熊の掌を調理した。著者はこう感想を綴る。
出てきた料理は、クマの手の姿煮。爪と骨を抜き、ひたすら煮込んだものなので、手の形がそのままだ。味付けも醤油ベースの薄味ソースだから、クマそのものの味を堪能できる。さっそくナイフで切り分けると、ゼラチン質の塊だけではなく、肉もしっかりついていて、一緒に食べたら、ぷるんとした食感とホロホロの肉が相まって、お世辞抜きで旨く、八角の香りも効いている。とはいえ、どんな味と訊かれたら、これまでの人生で未体験の味とでも答えるしかないのだが。
有害鳥獣対策は地域振興にも貢献
ジビエが注目されているのは、有害鳥獣問題とも無関係ではない。農林水産省によると、2022年度のシカやイノシシ、サル、カラスなど野生鳥獣による農作物被害額は156億円、森林の被害面積は全国で年間約5000ヘクタールに及ぶ。水産被害ではカワウによるアユの捕食などが報告されている。
その対策として捕獲(駆除)した鳥獣の肉を無駄にせず、ジビエ料理の食材として利用する流れが出てきた。著者は「肉を販売して利益を上げられれば地域経済の活性化につながる。上質の肉を提供して評判になれば地域のブランド力を高める効果がある。野生動物たちを迷惑な存在として片づけず、資源として捉える発想が生まれてきた」と評価する。

服部夫妻が獲り、冷凍していたマガモを焼く常連客(2024年4月10日、割烹「山鳥」)=泉宣道撮影
著者はジビエの流行は一時的なものではないとも主張している。なぜなら、有害鳥獣対策として「継続的な駆除活動をしていかなければならないからだ」。しかし、狩猟免許の所持者は1975年度の50万人超から、2019年度は約21万人。しかも約6割は60歳以上と高齢化も進んでいる。
環境省の統計では、22年度の捕獲頭数はシカが72万頭(うち狩猟15万頭)、イノシシが59万頭(同10万頭)だった。だが、捕獲されたシカ・イノシシのうちジビエとして食肉加工・流通された割合は約1割にとどまっている。大部分が廃棄されているのが現状だ。
野生動物の狩猟や捕獲はいわば「命」をいただくこと。国連の持続可能な開発目標(SDGs)の観点からも、食材やペットフード以外でもジビエを利活用すべきだろう。例えば、狩猟免許を持つジビエふじこ(本名:福岡富士子)さんが主宰する「狩女(かりじょ)の会」ではイノシシやシカの皮をなめして革細工のバッグや財布などの商品をつくっている。
和風ジビエの可能性を広げる新たな物語は始まったばかりだ。そのさまざまな魅力は、コロナ禍明けで激増している訪日外国人たちをも惹(ひ)きつけるかもしれない。