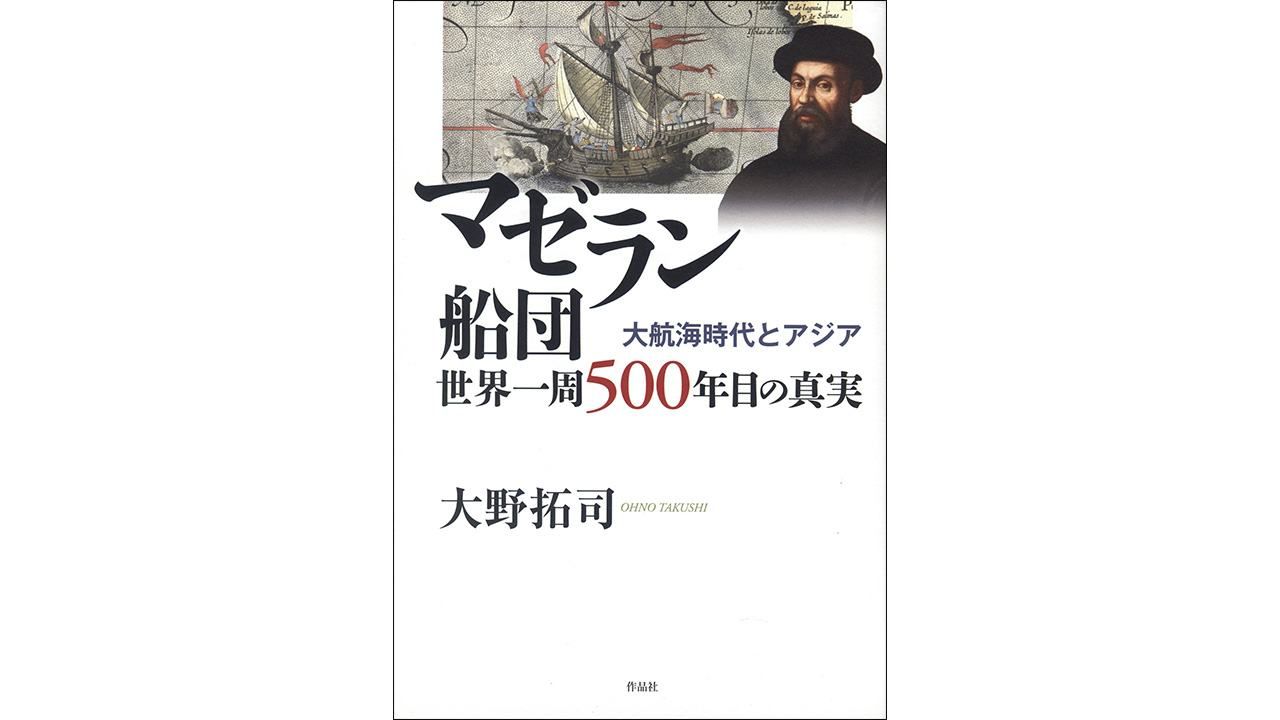
【書評】日本とフィリピンの歴史も描く:大野拓司著『マゼラン船団 世界一周500年目の真実──大航海時代とアジア』
Books 歴史 国際・海外 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
豊かなアジアと貧しいヨーロッパ
マゼラン船団とは、ポルトガル出身のフェルディナンド・マゼランが率いたスペイン帝国の5隻の艦隊。1519年にスペインから船出した野心家のマゼランが求めたのは「海外領土とスパイス(香辛料)」だった。ヨーロッパでは当時、胡椒(こしょう)などは大変高価な貴重品で、海外遠征に「命を懸ける価値」があったのだ。
1521年、船団は今日のフィリピン中部に到達した。しかし、マゼランはセブ島近くのマクタン島での地元民との戦闘で討ち死にしてしまう。配下のスペイン人フアン・セバスティアン・エルカーノが船長を引き継ぎ、翌22年に最後の1隻でスペインに帰還、世界一周を成し遂げた。

多島国フィリピンでは海に沈む夕日が美しい(1996年11月29日、比中部ボラカイ島)=評者撮影
本書は「マゼラン・エルカーノ遠征隊」の3年に及んだ“難航”の真相を克明に追っているのが前半のハイライトだ。船団に同乗していたイタリア出身のアントニオ・ピガフェッタによる詳細な「航海記録」など膨大な資料を渉猟し、著者自らも各地の現場を取材している。
マゼランの時代、「中世末期ヨーロッパは、相対的に貧しかった」。一方、「今日『アジア』として知られる一帯は比較的豊かだった」。著者はこう前置きし、時代背景を次の通り分析している。
黄金・絹・陶磁器など魅力的な物産の数々。当時、断片的に伝えられるアジアからの情報は、ヨーロッパの人びとの想像力を刺激し、冒険心と野望をかきたてた。それがマゼランを後押しし、「豊かなアジア」へと向かわせたのだ。
「大発見時代」は大虐殺・大略奪時代
コロンブスの新大陸「発見」、バスコ・ダ・ガマのインド航路開拓、そしてマゼラン・エルカーノの地球一周は“世界三大航海”といわれる。「(地理上の)大発見時代」(Age of Discovery)とも呼ばれてきた。
著者は「発見された側」からすれば「大虐殺の時代」であり、「大略奪の時代」でもあったと喝破(かっぱ)する。マゼラン船団の実態も暴く。
マゼラン・エルカーノ遠征隊も各地で乱暴狼藉を働いた。現代の視点にたてば、強盗、殺人、放火、拉致の数々。ピガフェッタは、そうした場面を淡々とした筆致で綴っている。
ちなみに、大発見に代わる「大航海時代」(Age of Navigation)というキーワードは日本の研究者が1960年代前半に考案したという。日本では学術用語として定着しているが、「欧米では、現在もなお『大発見時代』が一般的に使用されている。『ヨーロッパ史こそが世界史』との意識は根深く残っているのであろう」と著者は指摘している。
アジアの遠洋航海は西欧に先行
その著者はヨーロッパ中心の歴史観に異議を申し立てる。
アジアに目を転じると、異なる側面が見えてくる。早くも一三世紀後半、モンゴル帝国の皇帝フビライ・ハンが仕立てた艦隊が、南シナ海からジャワ海やインド洋に遠征した、という史実が浮かび上がる。初めて遠洋の南方航海ルートを開いたのだ。
西ヨーロッパが主導した大航海時代は15世紀から17世紀半ばにかけてである。だが、外洋航路の開拓はアジアが先行していた。最も有名なのは中国・明朝の武将、鄭和(ていわ)の「南海大遠征」だ。鄭和は1405年以降、7回にわたって大船団を率い、南シナ海、インド洋、アラビア半島、アフリカ東岸まで遠征を繰り返した。本書によると、最大時の船団は全長約140メートルの大型帆船ジャンクを60隻あまり連ね、計2万5000人以上の兵員を乗せていたという。
ジパング、邪馬台国はフィリピン?
著者、大野拓司(おおの・たくし)氏は1948年生まれ。70~77年に「マニラで遊学生活を送った」。朝日新聞記者となり、マニラ、ナイロビ、シドニーの各支局長を歴任した。南アフリカの喜望峰やイベリア半島、セネガル、アンゴラ、モザンビーク、マラッカ、東ティモール、ソロモン諸島など大航海時代ゆかりの地もあちこち訪ねたという。土地勘があるだけに、本書の記述は臨場感にあふれている。写真や図版が満載されており、大航海時代の歴史絵巻のようでもある。
スペインの植民地になったフィリピンのキリスト教とイスラム勢力とのせめぎ合い、今日のグローバル化の嚆矢(こうし)ともいえる16世紀後半から1815年までの「ガレオン貿易」(スペイン領マニラとメキシコのアカプルコを結ぶ木造大型帆船「ガレオン船」による太平洋貿易)などは読み応えがある。
当時のフィリピンと日本、中国との複雑な三角関係、さらに日本とフィリピンの交流の歴史も丁寧に描いている。
マゼランがフィリピン中部のビサヤ地方に到達する五〇〇年前に、すでに日本人がルソン島やミンドロ島、さらにはミンダナオ島に足跡を残している。
日比関係は1000年に及ぶ。旧日本軍は先の太平洋戦争でフィリピンに侵攻したが、実は戦国時代にも確執があった。豊臣秀吉の時代は朱印船貿易が盛んだった。ところが、「権勢を誇る秀吉は、マニラも影響下に置く野望を抱いていた」。秀吉は1591年と92年にマニラのスペイン総督宛に「降伏を勧告し入貢を求める書簡」を送ってどう喝したが、朝鮮出兵を優先したため、マニラ攻めは結局立ち消えになった。

日比間は古来、船の往来が多く、ペルシャ湾に向かう海上自衛隊の掃海艇部隊も寄港(1991年5月4日、ルソン島スービック米軍基地)=評者撮影
本書には学者らによる“新説”も盛り込まれている。13世紀に生まれたベネチアの商人で旅行家のマルコ・ポーロが『東方見聞録』に記した黄金の島「ジパング」は日本というのが通説だが、「フィリピン諸島を中心にした多島海地域」説を紹介している。
もっと大胆なのは、日本古代史最大の謎とされる「邪馬台国」はフィリピンの「ルソン島西側の平野部」という仮説だ。著者は「従来、九州説や近畿説が有力とされてきた邪馬台国。しかし、それがフィリピンだとすれば、卑弥呼は、今流にいえばフィリピーナだった」と説く。
「大航海時代」をめぐる世界史
| 1298年 | ベネチアの商人マルコ・ポーロの『東方見聞録』 |
| 1405年 | 中国・明朝の鄭和「南海大遠征」開始、アフリカに到達 |
| 1492年 | イタリアの航海者コロンブス、新大陸を「発見」 |
| 1494年 | ポルトガルとスペイン、海外分割のトルデシリャス条約 |
| 1519年 | 探検家マゼランが率いる船団、スペインの港を出航 |
| 1521年 | マゼラン船団がフィリピン中部に到達、マゼランは討死 |
| 1522年 | マゼラン船団の後継船長エルカーノがスペインに帰還 |
| 1549年 | イエズス会士フランシスコ・ザビエル、薩摩に上陸 |
| 1550年 | ポルトガル船、平戸に初入港、「南蛮貿易」開始 |
| 1565年 | スペイン、フィリピン中部セブ島で植民地統治に着手 |
| 1584年 | スペインのガレオン船、マニラから平戸に初入港 |
| 1591年 | 豊臣秀吉、マニラのスペイン総督に書簡で降伏を勧告 |
| 1602年 | 徳川家康、マニラ総督に書簡でキリスト教布教厳禁伝達 |
| 1613年 | イギリス、平戸に商館を開設(1623年閉鎖) |
| 1614年 | 徳川幕府がキリシタン国外追放令、高山右近はマニラへ |


