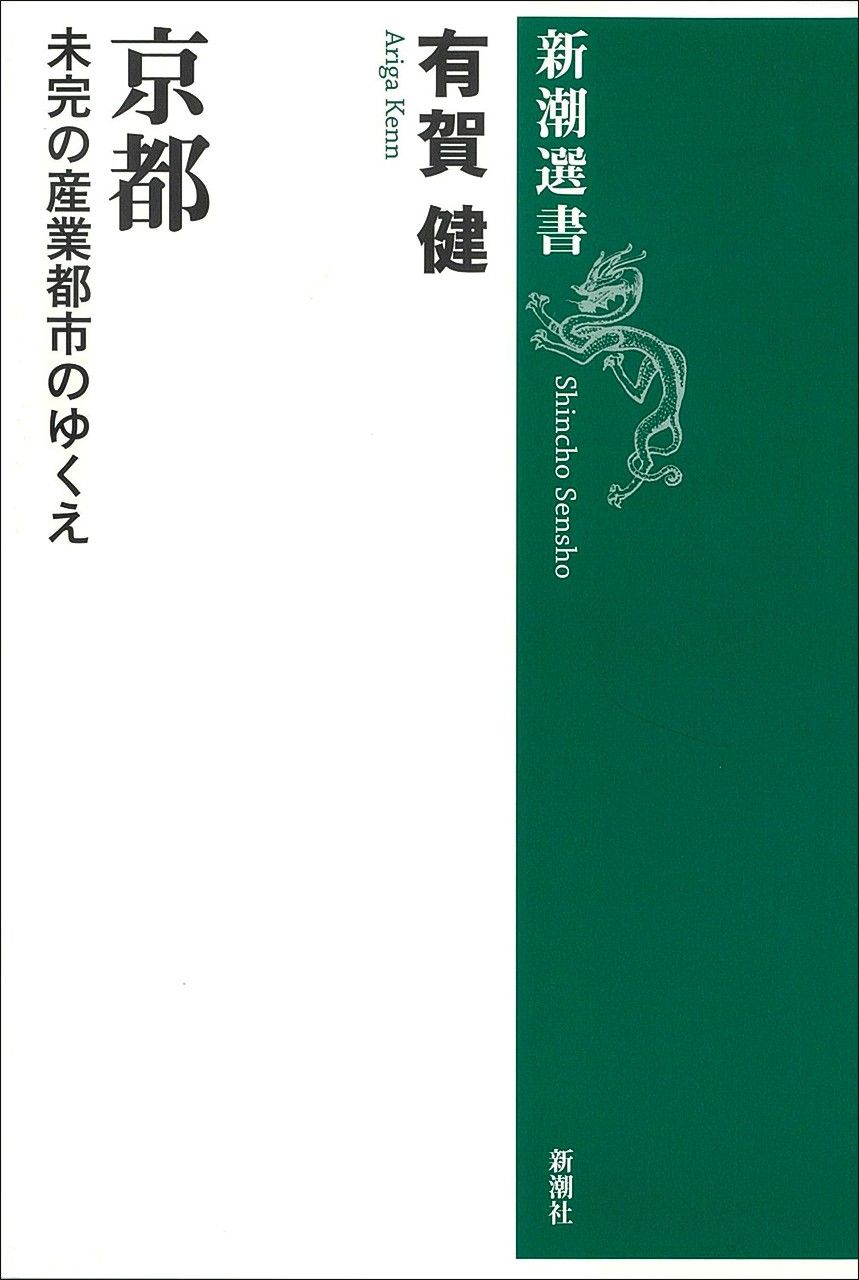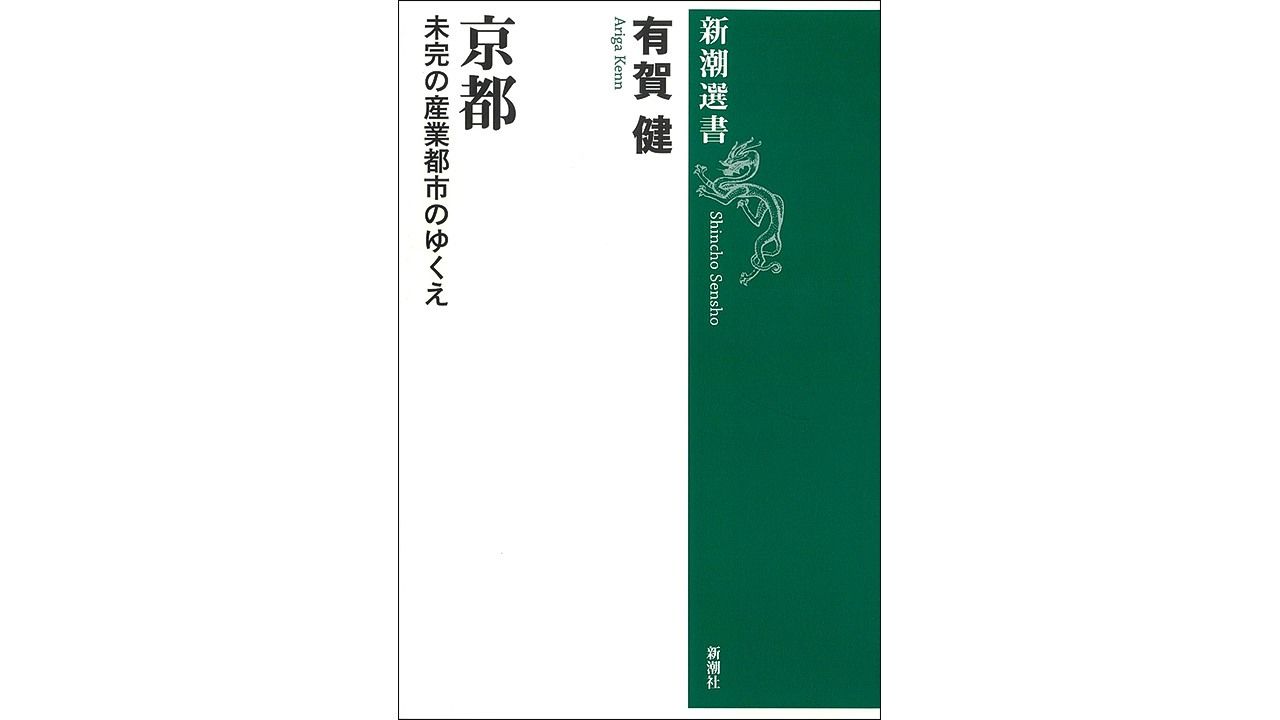
【書評】観光業の隆盛が京都の衰退を招いている:有賀健著『京都 未完の産業都市のゆくえ』
Books 旅 食 文化 経済・ビジネス- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
京料理は和食の代表なのか?
経済学者で京都大学名誉教授の著者は半世紀にわたって京都に住んでいるが、「現代の京都について決まり文句のように繰り返される表現の実証的な根拠が贔屓目に見ても薄弱であり、緻密な統計的検証を経たものではない」と記す。それはどういうことなのか。
本書の特徴は、明治維新以降の京都という町の変遷を、人口、産業、労働、交通など数々の統計データを駆使して分析した点にあるが、まずは最も分かりやすい事例から紹介しよう。「京料理に対する手放しの礼賛はその典型」として、著者はこう断ずる。
京都のレストラン、特に和食については、観光に関わりなく、常にゆるぎない地位を持つものであったと思われる方も多いだろうが、実はそうではない。
京都の食が隆盛を迎えたのは比較的最近のこと。事業者統計で飲食店の従業員比率を見ると、大阪、福岡、神戸と比べ、京都の盛況はバブル期以降である。著名な食の検索サイトを調べれば、人気上位50店舗のうち2000年以前にオープンしていたのは10店にすぎず、40店舗はそれ以降の創業だった。
そもそも懐石料理の起源は大阪の「吉兆」であり、もともとの京料理とは「豊富な蔬菜(そさい)と塩干物を利用した『いもぼう』のような『炊き合わせ』に代表される、質素な家庭料理」であった。京都の海産物といえば保存可能な塩サバと鱧(はも)しかなかったのだ。
京都の和食が現在の「名声と繁栄」を得た理由は、「裕福な旅行者がレストラン需要を大きく引き上げた」ことと、「高速道路の発達と冷蔵冷凍技術の進化により、京都市内でも十分に新鮮な魚介類が提供できる条件が整えられた」からである。結果、主要なレストラン・料亭は、上・中・下京区と祇園など狭いエリアにその6割が集中するようになったのだ。
京都の担い手は「町衆」
本書の主要なテーマは産業都市としての京都の変遷だが、いまだ未完のままであるという。かつて京都の産業といえば西陣織に代表される繊維関連が中心で、その担い手は中小の自営業者だった。彼らは「町衆」と呼ばれ、祇園祭の運営をはじめ、京都の自治組織の中心である。著者によれば、
1960年代に入っても市の中心部は、瓦屋根の町屋が並びいわゆる「田の字」と呼ばれる碁盤目の町を形成し、1車線を確保するのがぎりぎりの通りで区切られていた。近代化以降の京都の地域社会は、室町の商工業者、西陣に代表される職人たちを中核として発展した。(略)彼らの優位が続いたことにより、京都は、東京や大阪に見られた産業都市への変貌を果たせないまま高度成長期を迎えたのである。
京都は任天堂、京セラ、村田製作所など多くのハイテク企業を輩出したではないか、と反論する向きもあるだろう。こうした企業を指して「西陣織や清水焼といった伝統産業に結び付け、ものづくりの歴史がこれらの企業群が誕生した背景にあることが力説される」が、その言説にも疑問符がつく。著者はこう記す。
むしろ注目すべきは、これらの京都出身のハイテク企業が、京都の中心部や西陣、あるいは京焼(清水焼)の本拠である東山山麓にではなく、南西部に立地し、高度成長期後半に急成長したという事実である(略)これらの京都出身の企業においても急成長の途上から生産事業所は内外に分散されていて、その際立った特徴は、京都から外に出ることで成長したことにある。
なぜなら、中心部にオフィスビルを構えることはかなわない。京都は景観保護のために厳しい建築規制や様々な条例を設けており、「高度経済成長期の日本で例外なく見られた、都心部の高層化が京都の都心では起こらなかった」のである。
こうした規制を設けるようになった嚆矢(こうし)が7期28年(1950~78年)に及ぶ京都の革新府政であり、それを支持したのが外ならぬ「町衆」だった。なぜ京都には「古い町並みが残っている」のか。それは、「空襲被害を免れたからではなく」「西陣や室町が京都の主人公」であったために、「町屋の続く家並みは1990年代に入るまで都心部に残った」ということなのである。
人口が純流出を続ける最大の都市
しかし、続くバブルの崩壊によって「西陣と室町の衰退が決定的」となるが、それに代わる産業は育たなかった。その原因は景観保護規制による都市計画の不備と、交通インフラ整備の遅れにあるという。そして今や、2010年以降のインバウンド・ブームによって、潤っているのは新たに進出してきたレストランを中心とする観光関連の小規模事業者となった。著者は、「成功しすぎた観光都市としての京都が、観光以外の産業を抑圧している可能性がある」と指摘する。そしてこう嘆くのだ。
京都はバブル崩壊の頃を境に、その町並みや産業構造、更には地域社会も大きく変化し、観光都市としての姿がより鮮明になるにつれ、変化は加速した。京都は戦後長く続いた停滞から抜け出したものの、町衆の本拠としてのアイデンティティを失い、今や漂流しているように思える。
京都市は人口が純流出を続ける最大の都市である。純流出は20代前半から30代にかけて続き、10歳未満も純流出が続くことは、就業機会に恵まれず、子育て世代にも良好な住環境を提供できていない何よりの証拠である。
皮肉なことに、観光業の隆盛が京都の衰退を招いている。過熱した観光ブームが去ったとき、京都はどうなるのだろうか。