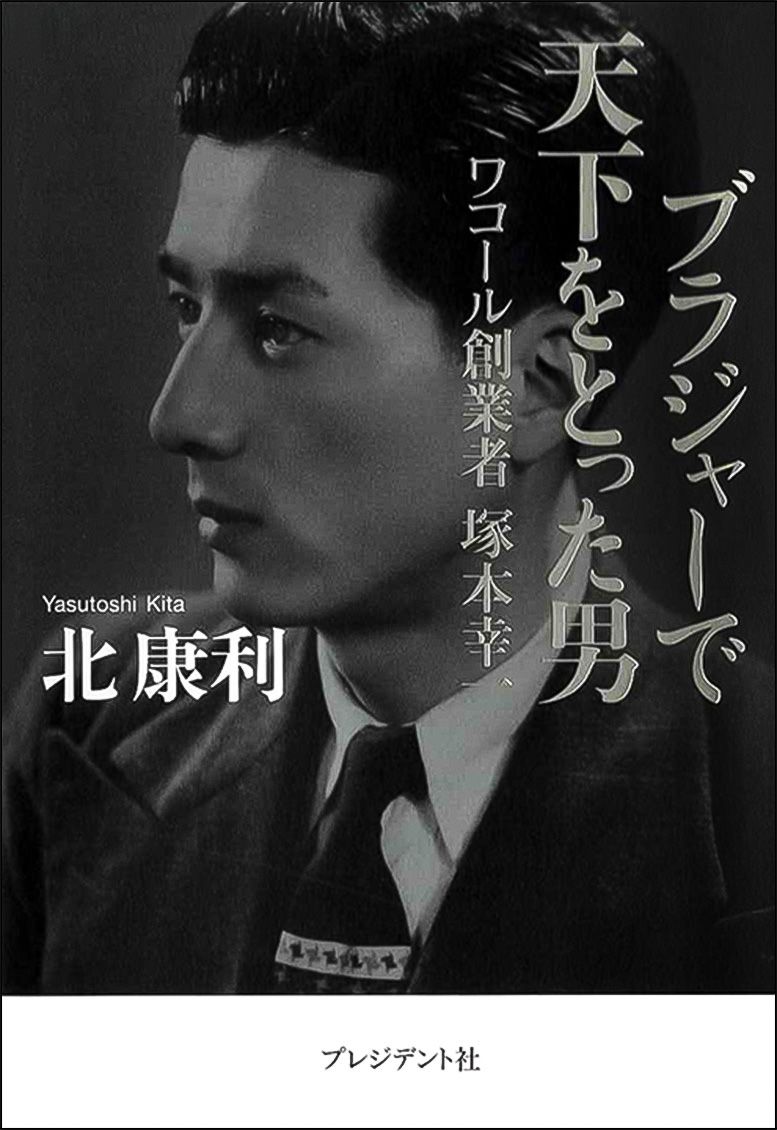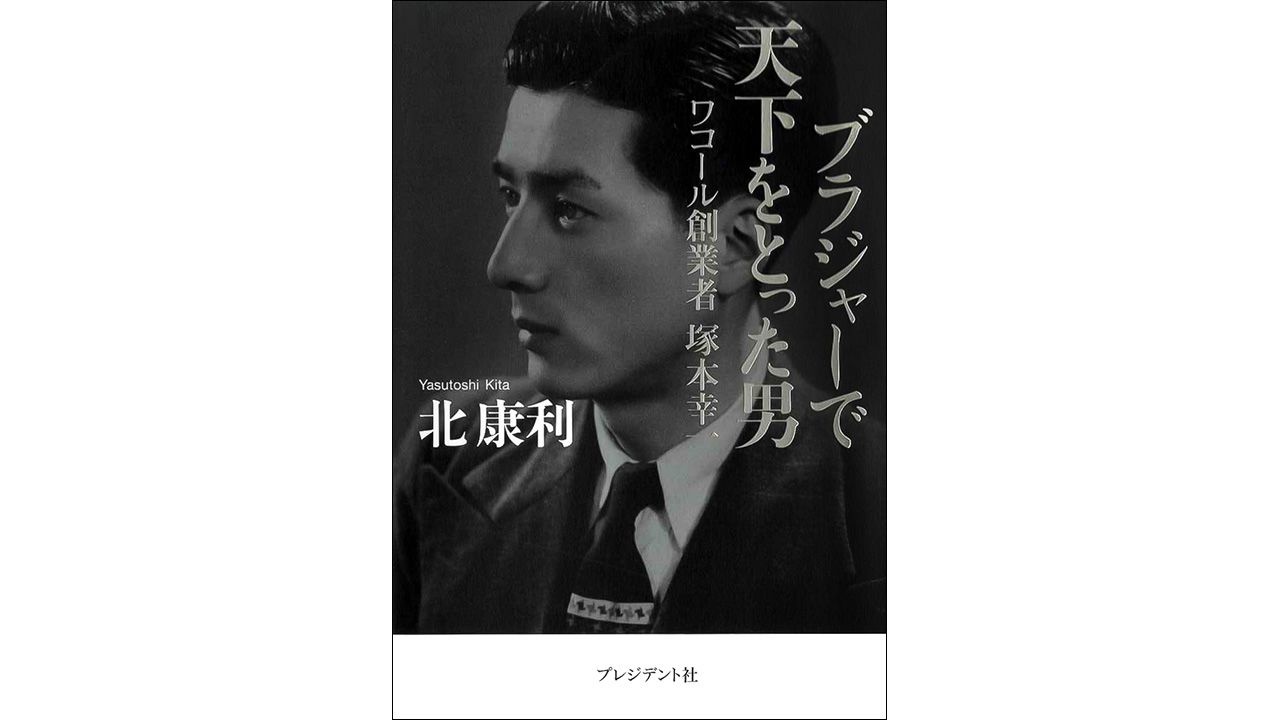
【書評】覚悟を持った軽やかさ:北康利著『ブラジャーで天下をとった男 ワコール創業者 塚本幸一』
Books 歴史 経済・ビジネス 仕事・労働 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
太平洋戦争のなかでも「史上最悪の作戦」と呼ばれ、凄惨(せいさん)を極めたインパール作戦。イギリス領インド帝国の攻略を目指した日本軍の無謀な行軍は、3万の死者を出す惨敗に終わった。
ビルマのジャングルをさまよって飢餓と疲労で倒れた兵士たちは、敗走の途上で腐敗し、骨と化していった。ついた名前が「白骨街道」だ。
インパール作戦に参加した55名の部隊の一員として戦地に渡り、生き残った3人のうちの1人が今回の主人公だ。
思い立ったらすぐ行動
その青年、塚本幸一が日本に帰国したのは26歳の時。
本書では彼が下着メーカーのワコールを起業し、業界一、さらには海外へと進出させていった過程を描いているが、混沌(こんとん)とした戦後の雰囲気、そして日本全体が飛躍的に経済成長を遂げようという時代の熱気と重なって、下手なドラマよりはるかに面白い。
ワコールといえば、いわば「下着の王道」。デパートの売り場では大きな面積を占め、若い頃にはとても手が出ない。そんなイメージだ。
会社もさぞ上品な始まりだったに違いないと予想していると、面白いほど裏切られる。
闇市での女性向けのアクセサリー販売にはじまり、一面識もない仕入れ先の社長に感動して、手持ちの金をすべて送ってしまう。アポの取れない社長相手には変装して深夜まで待ち伏せし、東京に行くと決めたら、すし詰めの夜行列車に窓から体を押し込み、立ったまま10時間揺られることもいとわない。
思い立ったらすぐ行動。京都からどこへでも出かけていき、文字通り汗水垂らしてひたむきに商売にまい進する姿は、ただひたすらに泥臭い。
デパートの店頭に置かれたマネキンがまとう、ひらひらしたレースに縁どられた高級下着とはまったく別の世界の物語だ。
自ら「エロ商事のエロ社長です」とおどけて見せながらも、幸一の目は笑っていなかった。
自分には亡くなった52人の戦友の分まで生きる責任がある。ここで弱音を吐くわけにはいかん
終戦から何十年が経っても、インパール作戦時代の悪夢にうなされ、夜中に汗びっしょりで飛び起きることもしょっちゅうだったという。
人材が得られる人
デパートで開催されたライバル企業との“公開売上合戦”や、男性をシャットアウトして行われた“下着ショー”など、塚本のアイデアと行動力が生んだおもしろいエピソードはほかにもたくさんあるが、この若き起業家の魅力は、なんといっても「人たらし」なところだろう。
ズルをすることなく常に正直でまっすぐ。ここぞと思ったらどんな破天荒な方法でもやり切ってしまう。豪放磊落(ごうほうらいらく)で気配りができて(だからモテる!)、部下に対しては誠実だ。
ああ、一緒に働いてみたかった!
そう思わずにはいられない。
「(幸一は)徳があるんです。人材の得られる人と得られない人では違ってきます。人材の得られる人は、やっぱりトップになっていきますわね」
幸一にスカウトされ、のちにワコールで女性初の課長となった渡辺あさ野の言葉だ。
渡辺に代表されるように、ワコールはこの時代の日本企業には珍しく、女性が活躍する土壌も培われていた。
縫製も、営業も、販売も……成長を引っ張っていったのは元気のいい女性たち。幸一は、事業に必要だと判断すると、男女の区別なくすぐに声をかけ、採用し、活躍の場を与えていった。
女性たちが楽しく過去を振り返る
この「女性活躍」という言葉が、日本企業について回るかけ声になってからずいぶん経つ。管理職に占める女性の割合などに数値目標を置き、目標を達成するためにさまざまな研修を行っている会社も多い。
それでも残念ながら、国際比較では常に下位にランクされ続ける現実に、失望している女性も少なくないと思う。時代背景は違っても、ワコールで塚本が軽やかに成し遂げた女性の採用や重用には学ぶところが多い。
近江の商人一家に生まれ、名門・八幡商業学校で学んだからなのか、幸一は「女性活躍!」という御旗を振りかざすわけでもなく、誰に何をやらせれば事業が伸びるのか、1円でも多く儲けるために必要な人材は誰かというシンプルな考えを貫き、ワコールの成功を形作っていった。
時代を考えれば、決して簡単なことではなかったはずだ。それもまた、軽やかに成し遂げてしまう。
性別も肩書も関係なく、仕事で評価され、優秀な人間には誰もが敬意を持って接する。ワコールで働いた若かりし日々を振り返る女性たち(多くが後期高齢者)が、みんな楽しそうに話すのは、そんな幸せな風土があったからではないだろうか。
それは、塚本幸一という希代の人たらしが持つ軽やかさと、彼が心に終生抱えていた、失った仲間の分まで生きるという覚悟の双方が生み出した果実なのだと思う。