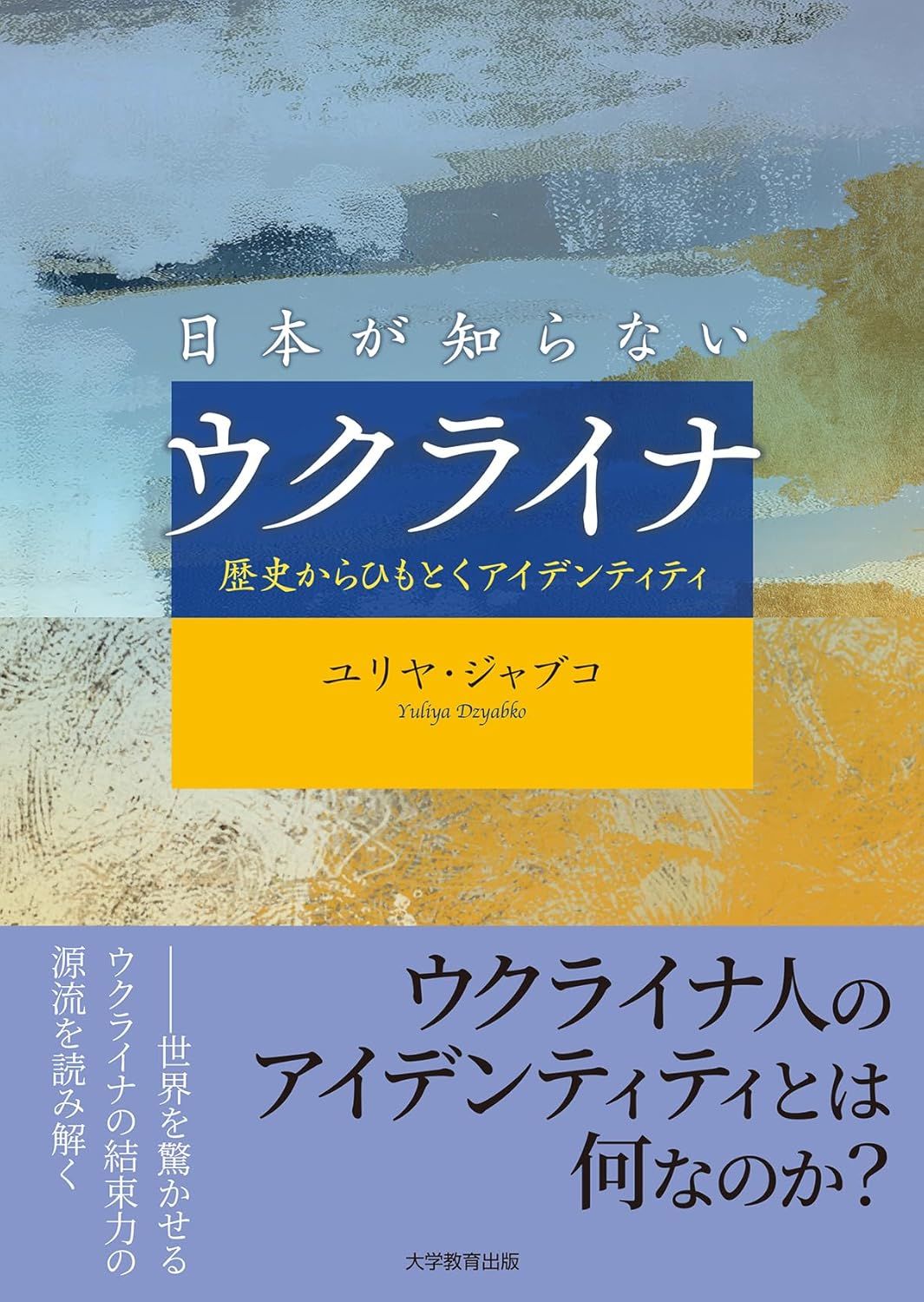全面侵略3年 日本はどう変わったか? ウクライナ人研究者の視点から
国際・海外 政治・外交 安保・防衛 国際交流- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ロシアのプロパガンダ
私が初めて日本に来たのは2006年9月、半年間の日本語学習プログラムだった。それは私にとって初めての海外渡航だった。そして、日本の人たちがウクライナのことをほとんど知らないという事実を初めて知ったのも、このときだった。
私が「ウクライナから来ました」と自己紹介すると、ロシアへ行ったことがない私に、多くの日本人がロシアの気候、文化、文学について、なぜか当たり前のように尋ねてきた。さらに驚いたことには、日本ではウクライナの歴史、芸術がロシアのものとして認識されていた、もしくは全く知られていないことだった。「ウクライナはロシアではない」と繰り返し説明しつつも、私はウクライナに対するゆがんだイメージがなぜ醸成されたのかを次第に考えるようになった。
日本において、なぜウクライナが「ポスト・ソビエト国家」として、しばしばロシアの影響圏内の国と見なされてきたのか? その一因は、帝政ロシア、ソ連、そしてソ連崩壊後のロシア連邦が発信した情報を通してのみ、日本側がウクライナを認知してきたからだ。言い換えれば、ロシアは典型的な「植民地宗主国」として、支配下にあったウクライナから発言権を奪い、ウクライナについて「代弁」してきた。それが出版物の一部となり、メディアで一般化された。
ロシアがウクライナに関して発する偏った歴史観、プロパガンダがどれだけ危険か―。私がそれを改めて意識したのは14年のことだ。ロシアは同年2月、ウクライナの領土であるクリミア半島、さらにドンバス地方と呼ばれるウクライナ東部の一部を占領。日本政府はロシアを批判し、経済制裁を行ったが、当時の日本メディアはウクライナから発信される情報をよく分析せず、ロシアが発信する情報をうのみにしていた。「クリミアはロシアの歴史的な領土である」「ウクライナ人とロシア人は兄弟民族だ」「ウクライナにいるロシア語話者がロシア系住民だ」といった偽情報をそのまま流すことがたびたびあった。そうしたメディア報道も時間と共に先細りとなり、多くの日本人からは長引くロシアとの戦争への認識が薄れていった。
「身近な国」に
2022年2月24日、ロシアはウクライナに全面侵略戦争を開始した。日本政府はすぐさまウクライナへの支持を表明し、力による一方的な現状変更を試みるロシアを明確に非難した。岸田文雄前首相の「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」という言葉が、ウクライナ支持の大きな象徴となったことは今なお記憶に新しい。
10年前の反省からだろうか、日本メディアの報道ぶりは大きく変化した。現地ウクライナから生の情報を発信したり、少数だがウクライナを専門とする国内の学者らの見解を伝えたりして、ロシアの戦争犯罪、ウクライナの人道的危機をつまびらかにした。
当時、私は他のウクライナ人翻訳者と同様に、さまざまな日本メディアから翻訳の依頼をかつてないほど受けた。最初の半年間はほぼ毎日、テレビのニュースや番組の制作に没頭した。番組では、ウクライナの現状に加え、歴史や文化の解釈、ロシアがウクライナに対して強いてきた過酷な措置や対応(ウクライナ語の使用禁止など)など幅広いテーマが報じられ、10年前とは隔世の感があった。

日本のウクライナ支援への感謝を示すサイン=2024年11月17日、東京・新宿(ユリアーナ・ロマニウ撮影)
象徴的だったのは、日本の外務省がウクライナの首都名をロシア語表記の「キエフ」から、ウクライナ語表記に基づいた「キーウ」へ変更したことだ。メディアは一斉にそれにならっただけでなく、他の地名などもウクライナ語表記に変更した。例えば「オデッサ」は「オデーサ」、「チェルノブイリ」は「チョルノービリ」、「ドニエプル川」は「ドニプロ川」といった具合だ。
ウクライナ人の一人として非常に嬉しく思うとともに、日本の対ウクライナ観が確実に変わったと感じた瞬間だった。多くの日本人にとって、ウクライナは「知らない国」から「身近な国」へ変わったのだった。
高まる学習・研究熱
私は2012年から日本に在住し、現在は大学で教壇に立っているが、世界の多くの国々と同様、かつて日本の大学ではウクライナに関するカリキュラムはほぼ皆無だった。東・中央ヨーロッパ研究を専門とする教育機関においてさえ、ウクライナは基本的にロシアの視点で論じられ、グローバルな視点からは捉えられていなかった。その証拠に、約800ある日本の大学のうち、22年までにウクライナ語を一般科目として導入していた大学はごくわずかだった。
ある国の専門家になるには、まずその国の言葉で読み書きができなければ、本当の歴史や社会を理解することが難しいのは常識といえる。逆に言えば、ウクライナの歴史と言葉を広めることは、ウクライナについての正しい理解だけでなく、ひいては世界秩序を変えようとするロシアの野望をくじく国際的な連帯を強めることにつながる。それは、私の中で次第に確信へと変わった。
では、私にできることは何か? ウクライナへの関心をどう持続し、さらに高めていくのか? 勤務先の大学で開催した「ウクライナの歴史と文化」と題する公開講座が一つの答えだった。22年から3年連続で開き、毎回数十人が聴講してくれた。彼ら、彼女らの真剣な反応を受け、「ようやくウクライナ人自身が自らの歴史を語ることができる時代がきた」と、手応えを感じることができた。

公開講座でウクライナの歴史と文化について説明する筆者=2023年10月、茨城キリスト教大学(筆者提供)
昨年の公開講座に参加した70代の女性に、なぜ講座に興味を持ったのかを尋ねてみたことがある。彼女は「ウクライナの人々への手助けを始めたものの、ウクライナのことをほとんど知らなかった。支援するのなら少しでも知ることが大切だと思った」と話してくれた。素朴な吐露に胸が熱くなると共に、着実な一歩を実感した。
日本の出版市場でウクライナに関する新しい書籍が増えているのも歓迎すべきことだ。政治、歴史、軍事に関するものだけでなく、文学や今回の戦争の目撃者による日記など、翻訳を含めてさまざまなジャンルのものが登場している。ウクライナ人のアイデンティティーを真に理解する大きな一助となっている。
広がる草の根の連帯
この3年間でウクライナ人と日本人の交流は着実に深まった。現在、日本に住むウクライナ人は約4000人。その半数は日本政府の支援で避難できた人々である。在日ウクライナ人は民間非営利団体(NPO)など通じ、各地で開かれる国際交流イベントに参加したり、展覧会やウクライナ支援のための集会を開いたりしている。
その一例が、在日ウクライナ人を中心に発足した「Stand with Ukraine Japan(SWU Japan)」だ。ウクライナを支援する日本の人々とともに東京で月に2回、戦争反対を訴えるボードやウクライナ国旗を掲げ、平和デモなどを行なっている。

ウクライナの国旗を掲げて支援を訴える女性。街頭活動には日本人も多く参加した=2024年11月17日、東京・新宿(ユリアーナ・ロマニウ撮影)
ウクライナと日本との国際交流において、最も歴史のあるNPO「日本ウクライナ友好協会KRAIANY」も忘れてはならない。同協会が東京・三鷹市で運営する「カフェ・クラヤヌィ」で昨年5月に開かれた行事にも、多くの日本人が集まった。その一人、60代の男性は「歴史や文化などについて教えてもらい、交流が深まっている」と語った。地道な努力はしっかり実を結んでいるのだ。
日本におけるウクライナのイメージは、徐々に「自由と独立のために戦っている国」へと変わりつつある。「知る」「理解する」という過程には時間がかかるが、2国間の関係は常に人と人とのつながりから始まることを忘れてはならない。最後に、ウクライナ人として、日本の人々に心から感謝の意を表したい。
バナー写真:ウクライナへの支援を訴える「Stand with Ukraine Japan」のメンバーら=2024年11月17日、東京・新宿(ユリアーナ・ロマニウ撮影)